事業用不動産の売却時にかかる税金や費用とは?売却を成功させるポイントも紹介
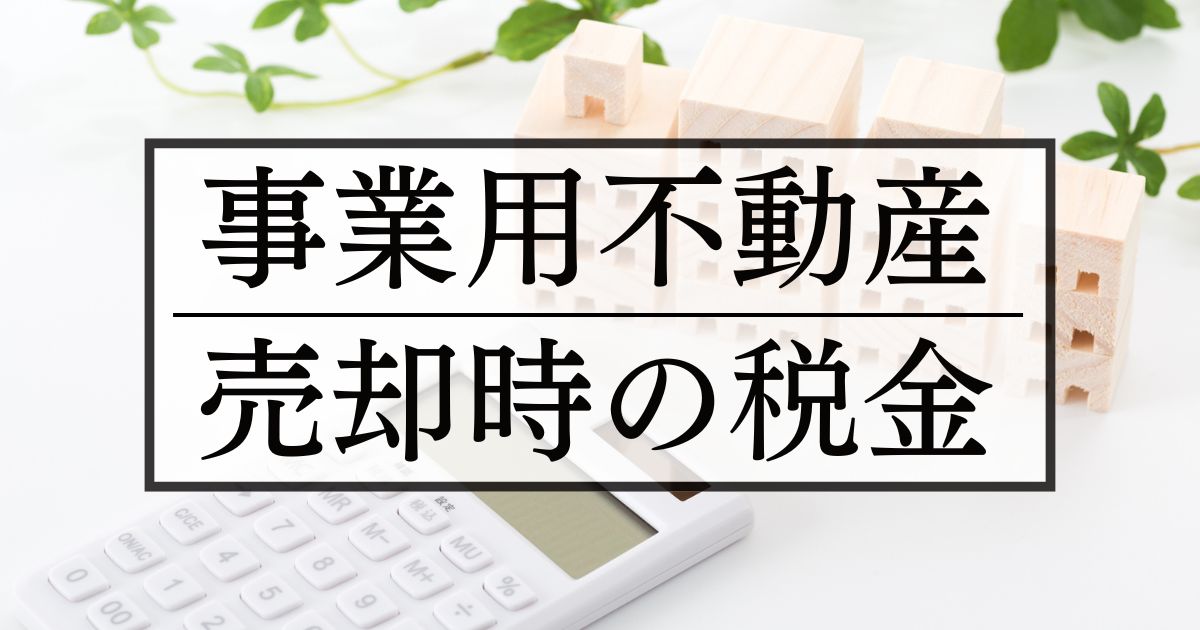
事務所やビル、店舗、マンション・アパートなど、収益化を目的として保有している不動産を事業用不動産といいます。収益があればメリットの大きい事業用不動産ですが、当然維持や管理には費用がかかるので、収益性が乏しい場合は売却を検討するのも一つの方法です。ただし、事業用不動産の売却には、さまざまな税金や費用がかかります。
事業用不動産売却時にかかる税金や費用、事業用不動産の売却を成功させるための4つのポイントを紹介します。
この記事の目次
事業用不動産を売却したときにかかる税金
事業用不動産を売却した際にかかる税金は、個人の場合か法人の場合かで変わります。それぞれの違いを見てみましょう。
譲渡所得税(個人の場合)
個人が事業用不動産を売却した際は、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は不動産売却によって発生する利益に対してかかる税金のことで、所得税と住民税を合計したものです。ただし2013年に施行された特別措置法により、2024年現在は復興特別所得税も含まれています(※1)。一般的に土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの譲渡で生ずる所得に課税されます。
事業用不動産を含め、土地や建物などの不動産売却で課税される譲渡所得税は、給与所得などそのほかの所得とは合算せず、分離して算出する「分離課税制度」が採用されています。個人が事業用不動産を売却した際は翌年に確定申告をして、所得税・復興特別所得税は申告の期限内に納めなくてはなりません。
譲渡所得税の対象となる譲渡所得は、以下のように計算できます。
「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」
譲渡所得が割り出せたら、税率をかけて税額を算出します。税率は、所有年数に応じて「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の二つのどちらかを当てはめます。それぞれの期間と税率の違いを詳しく見ていきましょう。
※1 参考:国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
長期譲渡所得
長期譲渡所得は不動産を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以上経っている場合の所得区分のことです。長期譲渡所得のほうが、後述する短期所得よりも課税率が低いです。
長期譲渡所得に対してかかる税金は以下のとおりです。
- 所得税:課税長期譲渡所得金額×15%(※1)
- 住民税:課税長期譲渡所得金額×5%(※2)
- 復興特別所得税:長期譲渡所得税額×2.1%(※1)
※1 参考:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
※2 参考:東京都主税局「土地・建物等の譲渡に係る所得税(国税)・住民税(地方税)」
短期譲渡所得
短期譲渡所得は不動産を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下の場合の所得区分のことです。
短期譲渡所得に対してかかる税金は以下のとおりです。
- 所得税:課税短期譲渡所得金額×30%(※1)
- 住民税:課税短期譲渡所得金額×9%(※2)
- 特別復興所得税:短期譲渡所得税額×2.1%(※1)
年度の途中に所有期間が5年を超えた事業用不動産でも、売却した年の1月1日時点で所有してから5年経過していなければ短期譲渡所得になるので注意しましょう。節税のためには、長期譲渡所得になるまで売却を待つのも一つの方法です。
※1 参考:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
※2 参考:東京都主税局.「土地・建物等の譲渡に係る所得税(国税)・住民税(地方税)」
法人税(法人の場合)
法人が事業用不動産を売却した場合は、譲渡所得税ではなく法人税がかかります。
法人税は、事業年度ごとに法人所得に対して課税される税金です。個人のように不動産売却による所得と区別することはなく、事業用不動産売却を含めたすべての事業による所得を合わせた総所得額に対して課税されます。そのため、事業用不動産売却によって利益が出たとしても、そのほかの事業で損失があった場合は損益通算して所得を減らせるため、節税できる可能性があります。
譲渡所得のように所有年数による税率の違いはありません。これまで法人が土地を売却した際は、法人税に加えて特別税率による追加課税が行われ、長期と短期で税率が異なっていましたが、1998年1月1日〜2026年3月31日までの譲渡については適用停止※となっています。
法人税の税率は、法人の区分によって異なります。
※参考:国土交通省「土地の譲渡に係る税制」
消費税
個人でも法人でも課税事業者であれば、事業用不動産を売却して利益が出ると利益に対して消費税が課されます。売却した不動産が土地の場合は、消費するものではないので課税対象にはなりません。
課税事業者とは、基準期間もしくは特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者のことです。個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度が基準期間です。また個人の場合の特定期間は、前年の1月1日〜6月30日までの期間、法人の場合は原則として前事業年度の年度開始日から6カ月間になります。
※参考:国税局「消費税のしくみ」
印紙税
印紙税は、売買契約書に貼付することで納める税金です。税額は、以下の表のように、契約価格により決まります。軽減措置が適用されており、印紙税額は以下の通りです。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
参照元:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記を行う際に課される税金で、登記の種類によって税額が異なります。
アパートを売却する場合、事業用ローンを利用していると、金融機関の抵当権が設定されているのが一般的です。この抵当権を抹消するには、ローンの残債を一括で返済し、抵当権抹消登記を行う必要があります。抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1筆につき1,000円です。たとえば、アパートが土地1筆と建物1筆で構成されている場合、登録免許税は2,000円となります。
登記手続きは多くの場合、司法書士に依頼します。司法書士に依頼した場合、登録免許税や司法書士報酬、交通費などを合わせた金額を、決済時にまとめて支払うことになります。司法書士報酬は事務所によって異なるため、事前に見積もりを取っておくことをおすすめします。
また、相続登記や売却時の所有権移転登記にも登録免許税が発生します。売却時の所有権移転登記にかかる登録免許税は、通常、買主が負担します。
事業用不動産の売却に必要な費用
事業用不動産を売却する場合、税金以外にもさまざまな費用が必要になります。
| 仲介手数料 | 不動産会社に仲介してもらう場合に発生する手数料 |
|---|---|
| 立退料 | 賃貸物件で貸借人に立ち退きをしてもらう場合にかかる費用 |
| 建物取り壊し費用 | 建物を取り壊して売却する際にかかる費用 |
| 違約金 | 売却のために管理委託契約を途中解除した場合に発生する費用 |
| 名義書換料 | 借地権売却のために地主に対して支払う費用 |
| 登記関係費用 | 登録免許税・司法書士報酬・抵当権抹消費用 |
| 測量費用 | 土地の測量にかかる費用 |
| 移転・不用品処分代 | 引っ越しや不用品の処分を買取事業者に依頼する際にかかる費用 |
| 消費税 | 仲介手数料や司法書士報酬などに課される税金 |
事業用不動産の売却を成功させるためのポイント
最後に事業用不動産の売却を成功させる4つのポイントを紹介します。
契約不適合責任に注意する
事業用不動産の売却を成功させるためには、契約不適合責任に注意しましょう。
契約不適合責任とは、売却した事業用不動産が契約内容と一致していない場合、売り主が負わなければならない責任のことです。売却した事業用不動産に告知していない欠陥があると、欠陥の補修費用や損害賠償を請求されたり契約解除になったりする恐れがあります。売却後にトラブルにならないように、契約前に欠陥がないかしっかり確認し、欠陥がある場合は必ず告知しましょう。
売却予定の不動産を貸し出している場合、利用者に通知しておく
売却を検討している事業用不動産を貸し出している場合は、利用者(貸借人)に対して通知が必要です。不動産の所有者が変わると、家賃などの支払い先が変更になるので、必ず事前に通知しておきましょう。
特例制度を活用できないか検討する
「売却した年の1月1日時点で10年以上所有している」など一定の条件を満たせば、事業用不動産売却時に発生する利益に対して、課される税金を将来に繰り延べることができる「事業資産の買い替え特例」が適用できます。課税割合は地域によって異なり、条件によっては適用期間も異なるので、注意が必要です。
こちらの記事でも詳しく紹介しています。
専門家である不動産会社に相談する
事業用不動産の売却を成功させるためには、不動産会社への相談も検討しましょう。
事業用不動産売却には、税金や必要書類の提出など、さまざまな専門知識が求められます。居住用と事業用では適用できる控除や建物の償却率が異なったりするため、専門家の手を仮ながら売却を進めるのがよいでしょう。売却にかかるコストを抑えながらスムーズな売却を実現するには、事業用不動産売却に強みを持つ不動産会社に相談するのがおすすめです。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
鈴木 和典
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





