アパート経営はやめたほうがいい?肯定派・否定派の意見と辞めどき解説
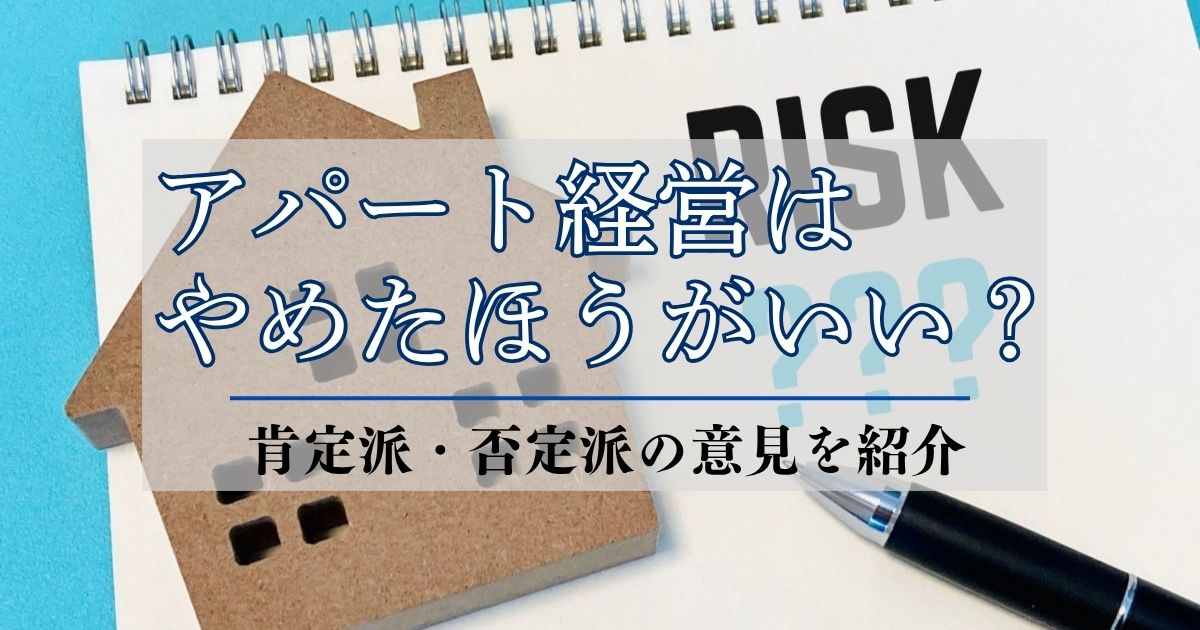
「アパート経営はやめたほうがいいのでは?」そんな疑問や不安を抱えている方が、近年とても増えています。家賃下落、空室リスク、修繕費の増加…収益が伸び悩み、「続ける意味があるのか」と迷うこともあるでしょう。
一方で、「まだ十分に利益を出せる」「工夫次第で安定経営できる」と語るオーナーも。この違いは何なのか。そして、もし辞めるとすれば、どのタイミングがベストなのでしょうか。
アパート経営の肯定派・否定派それぞれのリアルな声、そして「後悔しないやめどき」の見極め方を解説します。
この記事の目次
アパート経営はやめたほうがいい派の意見
アパート経営には、「やめたほうがいい」「素人には危険すぎる」といった否定的な意見も存在します。
ここでは、アパート経営に慎重な意見を持つ方の主張を見ていきましょう。
空室が埋まらないと赤字になりやすい
空室が増えれば家賃収入は減少します。その状態が続くと、経営は赤字になるでしょう。例えば、家賃が5万円の部屋が10戸あるアパートで、毎月のローン返済や管理費などのランニングコストが40万円だとします。
満室なら毎月50万円の家賃収入があり、10万円のプラスです。しかし、これが2部屋空室になると、収入は40万円になり、収支はちょうどプラスマイナスゼロになります。3部屋以上空室が出たら、その時点で赤字に転落してしまいます。
さらに、空室を埋めようとして家賃を下げれば、当初見込んでいた収入よりも減ってしまい、赤字のリスクはさらに高まります。特に、都心から離れた地方都市や築年数が古い物件では、人口減少や人のニーズの変化によって、入居者を見つけるのが難しくなっています。
なかにはアパートの空室率が3割を超えるエリアもあり、この傾向は今後も続く見込みです。
自然災害や老朽化で修繕コストがかさむ
築年数がたつにつれ、アパートは老朽化します。そのため、定期的なメンテナンスや大規模な修繕は不可欠です。
さらに、地震や台風といった自然災害が多い日本では、予測できない修繕費用が発生するリスクも常に頭に入れておく必要があります。
たとえば、築20年を超えたアパートでは、外壁の塗り替えや屋根工事、給排水管の交換といった大がかりな修繕が必要になることも珍しくありません。これらの費用は数百万円から、ときには数千万円にも及びます。
また、地震や台風、水害などで建物が損傷しても、火災保険だけでは補償が不十分な場合や、自己負担(免責)が発生することがあります。こうした突発的な出費は、アパート経営の収支を大きく圧迫し、資金繰りを困難にする原因となるでしょう。
人口減少や地域の衰退で資産価値が下がる
アパートの資産価値は、地域の経済状況や人口の動きに大きく左右されます。特に、人口が減り続けている地方では、その影響が顕著に出やすく、アパートの価値が下がるリスクが高まります。
人口が減ると入居者が見つかりにくくなって空室が増え、土地の価格自体が下落しやすくなるからです。そうなってしまうと、アパートを売却しようと思っても、買い手が見つからなかったり、想定していた価格で売れなかったりと、投資した資金が回収できず、大きな損失を抱えてしまうでしょう。
アパート経営は続けたほうがいい派の意見
「アパート経営はやめた方がいい」という声がある一方で、長期的に安定した収入を得られる魅力的な投資として、推奨する意見も多く聞かれます。
ここでは、アパート経営を続けるべきと考える人の意見を解説します。
安定収入を得られる資産として活用できる
アパート経営の大きな魅力は、なんといっても毎月安定した家賃収入が得られることです。
一度入居者が決まれば中長期にわたって安定した家賃が入り、比較的安定した収入源となります。うまくいけば、株式投資のように市場の変動に大きく左右されることがないのです。
例えば、複数のアパートを所有していれば、たとえひとつのアパートの入居率が悪化しても、他の物件からの家賃収入で一定の収益を確保できます。これにより、年金や給与以外の収入源として、生活の安定や老後の資産形成に貢献してくれるでしょう。
さらに、家賃収入はインフレにも強いという特性があります。物価が上がれば、それに伴って家賃も上がる傾向があるため、アパートの資産価値も上昇しやすく、インフレによる資産価値の目減りの影響を受けにくいというメリットもあるのです。
節税や相続対策に有効なケースもある
本業で所得税を多く払っている方や、相続税が多く発生する可能性のある方にとってアパート経営は、節税や相続対策として有効な場合があります。
まず、アパート経営は所得税の節税の面でメリットが挙げられます。アパート経営で生じる費用、例えば減価償却費、固定資産税、修繕費、管理費などは経費として計上できるため、所得税の課税対象となる所得を減らすことができるでしょう。
特に減価償却費は、実際にお金が出ていくわけではないのに課税所得を減らす効果があるため節税効果が期待できます。また、アパートやマンションといった不動産は、現金や株などの有価証券に比べて、相続税の評価額が低く見積もられる傾向です。
そのため、現金や株で資産を保有しているときに比べて評価額を大幅に圧縮でき、相続税を減らせる可能性があります。
エリアや物件次第で高利回りも期待できる
アパート経営は物件の立地や種類によっては、高い利回りを期待できます。特に、都心の駅に近い物件や、大学の周辺、企業の事業所が多いエリアなど、賃貸需要が高い地域では、安定して入居者を確保でき、高めの家賃設定も可能です。
また、地方都市であっても、特定の賃貸物件の需要が安定しており、今後も人口の流入が見込まれる地域であれば、高い利回りでアパート経営を成功させられる可能性は十分にあります。
さらに、たとえ築年数がたっている物件でも、リノベーションを施して魅力を高めることで、新たな入居者を獲得し、家賃を高く設定することも可能です。
最近では、シェアハウスや民泊といった多様な運用方法も登場しており、物件の特性に合わせて工夫すれば、収益性を高める選択肢はさらに広がっています。
アパート経営のやめどき・リタイア時期の見極め方
アパート経営を続けるべきか、それともリタイアすべきかは、非常に難しい決断です。
しかし、複数の客観的指標や状況の変化を把握できれば、適切なやめどき・リタイア時期を見極めやすくなるでしょう。
修繕費や管理負担が増えてきたら検討を
アパートは年数がたつにつれて老朽化が進み、それに伴い修繕費用が増えていく傾向にあります。
最初は小さな修繕で済んでいたものが、時間がたつにつれて大規模な修繕が必要になり、その費用が収益を圧迫し始めるようなら、そろそろ手放すことを検討するサインかもしれません。
例えば、外壁のひび割れ、屋根の劣化、給排水管の詰まりや水漏れ、共用設備の故障など、さまざまな修繕が頻繁に発生し、そのたびにまとまった費用がかかるようだと、資金繰りが苦しくなってしまいます。
さらに、入居者からのクレーム対応や設備の不具合に対する緊急対応など、管理業務の負担が大きくなり、精神的なストレスになる場合も、アパート経営を続けるかどうかを考えるべきポイントとなります。
入居率や利回りが大きく下がったときがサイン
アパート経営がうまくいっているかを判断するうえで、特に重要なのが入居率と利回りです。これらの数値が長期的に見て下がり続けているなら、それは経営が悪化している証拠であり、やめどきを検討する大きなサインといえます。
入居率が下がるということは、そのまま家賃収入の減少に直結します。例えば、以前はいつも満室だったアパートが、以下のような状況の場合、市場のニーズと物件の魅力がマッチしていないかもしれません。
- 数カ月にわたって空室が目立つ
- 募集をかけても入居者が決まらない
利回り(年間家賃収入÷物件購入価格)が大きく下がった場合も同様です。家賃の下落や空室、経費の増加で利回りが下がり、安定水準を下回る状態が続くなら、投資としての魅力は薄れたといえます。
これらの状況が改善される見込みが薄い場合は、保有し続けるよりも売却を検討するほうが賢明といえるでしょう。
売却益が出やすいタイミングを逃さない
アパート経営を終えるなら、物件を高く売れるタイミングで手放すのが理想的です。市場の動きを常にチェックし、売却益が出やすい時期を逃さないことが、経営を成功裏に終わらせるための重要なカギとなります。
不動産市場は景気や金利の動き、地域の再開発計画など、さまざまな要因で変動します。たとえば、大きな再開発が発表されたり、新しい交通機関が整備されたりすると、その周辺の不動産価格は上がる可能性があります。
また、金融政策の変更によって、投資家の購入意欲も変わってきます。金利が低い時期や、より有利な条件でローンを組めるようになれば、不動産を購入しやすくなるため、買い手も見つかりやすくなるでしょう。
アパートの築年数が比較的浅く、まだ大規模な修繕が必要になる前に売却すれば、より高く売却できる可能性もあります。不動産会社に定期的に相談し、現在の物件価値と市場の動向を把握しておくことで、最適な売却時期を見極められます。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
鳥塚 正人
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





