アパート経営で経費計上できるもの・できないものの違いとは?一覧表付
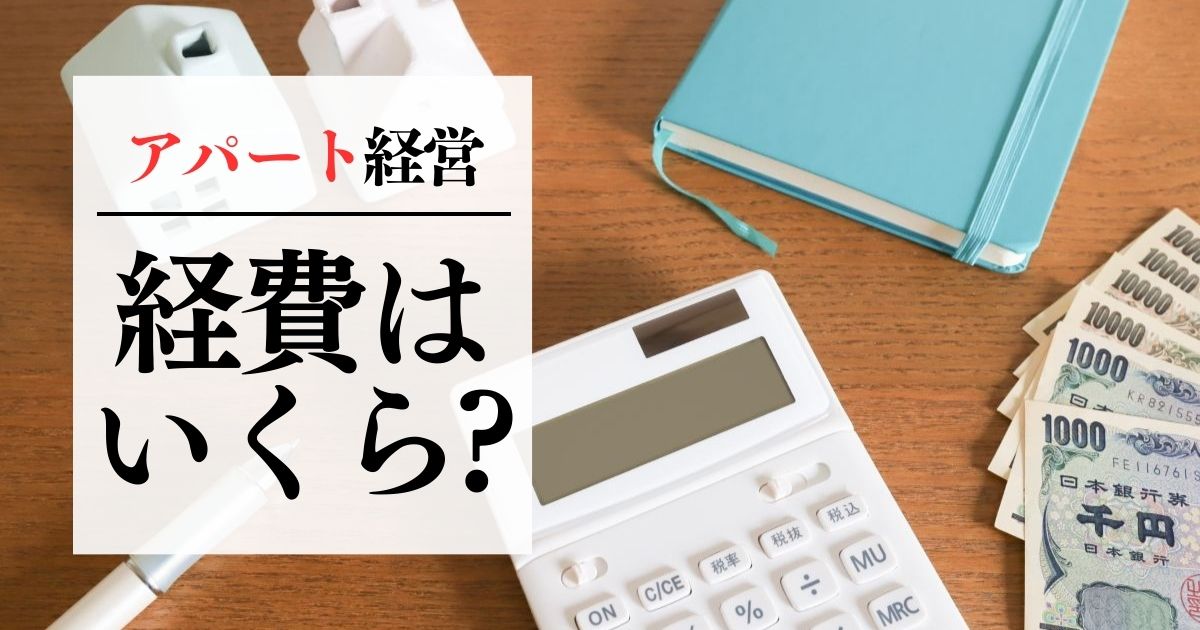
アパート経営では事業に関係する支出を経費に計上し、賃貸収入から控除して最終的な利益を計算します。経費として計上できる額が増えるとアパート経営の利益を圧縮できるため、節税につながるでしょう。
ここでは、アパート経営で経費に計上できるものとできないものを解説します。
この記事の目次
アパート経営で経費計上できるもの
アパート経営で経費に計上できるかどうかは、主に以下の基準で判断します。
- アパート経営に直接関連した支出である
- アパート経営の業務遂行上のために発生した経費であると証明できる
- 金額が不自然に高額ではなく、合理的と考えられる範囲内である
具体的には、以下のような支出や税金が経費として計上できます。
経費に計上できるもの
| 経費に計上できるもの | 具体例 |
|---|---|
| 車の購入費用 | アパートや取引先を訪問する車の購入など |
| 備品の購入費用 | 業務管理で使用するパソコンやカメラの購入など |
| 接待交際費/会議費 | 取引先への手土産代の購入など |
| 管理費/管理委託費 | 共用部分の清掃費用や水道光熱費、点検費用、管理会社への委託費用など |
| 修繕費 | アパートの設備や外壁の修繕など |
| 保険料 | アパートの火災保険や地震保険、施設賠償責任保険など |
| 借入金の返済利息部分 | アパートを購入するための借入金利息の返済 |
| 仲介手数料 | 不動産会社を介して入居者が決まったときの仲介手数料 |
| 広告宣伝費 | チラシやパンフレット、看板の制作費、不動産会社への広告料など |
| 事務手数料 | 金融機関や不動産会社、税理士などの事務手数料 |
| 保証料 | 保証委託会社への保証料 |
| 地代/家賃 | アパートを建てるための地代や事務所の家賃 |
| 青色事業専従者給与 | 従業員として働いている家族への給与支払い |
| 新聞図書費 | 新聞や雑誌、書籍など |
| 立ち退き料 | 賃借人に退去してもらうときの立ち退き料 |
| 不動産取得税 | アパートの購入価格に課税される不動産取得税 |
| 登録免許税 | 登記申請時に納税する登録免許税 |
| 印紙税 | 売買契約書や工事請負契約書に貼り付ける印紙 |
| 固定資産税 | アパートの評価額に課税される固定資産税 |
| 都市計画税 | 行政の都市計画に基づいて課税される都市計画税 |
それぞれについて詳しく確認していきましょう。
車の購入費用
アパートや取引先の訪問で使用するための車は、購入費用として経費扱いにできます。ただし通常、車の購入費用は一括では計上されません。
購入費用を法定耐用年数の期間で按分し、毎年少しずつ「減価償却費」として計上します。
法定耐用年数とは、使用期間として資産の種類ごとに法律上で定められた年数です。一定の価値がある資産は、資産の取得価値を法定耐用年数に応じて各年度に配分し、「減価償却費」として計上します。
計算例は以下のとおりです。
- 購入価格:240万円
- 耐用年数:6年(新車・普通自動車の法定耐用年数)
- 計上費用:年40万円(定額法により減価償却費として毎年計上する場合)
自家用車を兼用しているときは、以下のように事業で使用した割合とプライベートで使用した割合で按分します。例えば、以下のように計算します。
- 使用頻度:月8日事業で使用
- 計上費用:年40万円
- 按分額:年40万円×(8日×12カ月÷365)=年約10万5,205円
なお、購入額が30万円未満であり、オーナーが青色申告をしているときは、購入額を一括で経費計上できる少額減価償却資産の特例も利用できます。
備品の購入費用
アパートの管理で使用するパソコンやカメラなどの備品は、経費に計上できます。計上方法は購入額によって異なるため注意しましょう。
購入額が10万円未満であれば、「消耗品費」や「事務用品費」として一括で計上します。10万円以上の場合、「工具器具備品」などで貸借対照表に計上し、法定耐用年数の期間、「減価償却」で毎年少しずつ計上します。
接待交際費/会議費
アパートの管理会社や税理士など、業務上関わりがある取引先への交際費用は「接待交際費」として経費計上できます。例えば、お中元やお土産、飲食代、慶弔費用の支払いなどです。
取引先と打ち合わせをしたときの会場費用や使用代、飲食代などは「会議費」として経費計上します。飲食代は、令和6年度税制改正により1人あたり1万円以下であれば「会議費」として計上できるようになりました(2024年4月1日以後の飲食代に適用)。
「接待交際費」を損金に算入できる額について、個人事業主の場合は上限がありませんが、法人の場合は算入額に一定の上限があります。
法人の場合、可能な限り「会議費」として計上するほうが節税につながるでしょう。
管理費/管理委託費
アパートを維持管理するために支払った費用は、経費として計上できます。例えば、共用部分の清掃費用や水道光熱費、点検費用、管理会社への委託費用などです。
費用として計上する科目は「水道光熱費」「修繕費」「外注費」「業務委託費」など、管理の内容によって使い分けましょう。
修繕費
アパートの設備や外壁などを修繕するための支出は、「修繕費」として費用に計上できます。小規模な修繕であれば、支出した金額を一括で計上します。
一方で、大規模修繕など、修繕の効果がアパートの資産価値を高めるときや使用可能期間を延ばすときもあるでしょう。この場合、修繕費は「建物」や「附属設備」として計上し、毎月「減価償却費」として少しずつ計上していきます。
保険料
アパートに関する火災保険や地震保険、施設賠償責任保険などは経費に計上できます。計上方法は、契約期間で区別しましょう。
契約期間が1年未満の場合、保険料を支払ったときに全額を「保険料」などで計上します。契約期間が1年以上のときは、年度内で経過した契約期間に相当する分を計上し、残額は来年度以降で計上します。
借入金の返済利息部分
アパートを購入するときは、金融機関で借入れをして購入資金にあてるケースが多いでしょう。借入金には期間や利率に応じて利息が発生しますが、利息は事業の経費として損益計算書の「支払利息」に計上できます。
なお、個人の住宅ローンなど、アパートに関係ない借入金の利息は経費計上できません。
仲介手数料
不動産会社を介して入居者を募集し、成約したときの仲介手数料は経費に計上できます。
主に使用される勘定科目は「支払手数料」です。 アパートを購入したときの仲介手数料は、取得費用の一部として貸借対照表の資産科目である「建物」に計上されるため区別しましょう。
この場合、支払額を一括では計上できませんが、建物の「減価償却費」として毎年少しずつ経費計上できます。
広告宣伝費
アパートを広告するためのチラシやパンフレット、看板の制作費、不動産会社への広告料などは「広告宣伝費」で経費計上できます。
例外として、建物と一体となっている屋外広告であり、10万円を超えるようなときは「建物附属設備」に計上しましょう。
「建物附属設備」に計上したあとは、「減価償却費」で法定耐用年数の期間中に少しずつ経費計上します。
事務手数料
金融機関や不動産会社、税理士などに支払う事務手数料は、一般的に「支払手数料」の科目で経費計上できます。
アパート購入にかかる事務手数料のときは取得費用の一部となり、「建物」に計上して毎年少しずつ減価償却します。
保証料
アパートローンを契約するときなどは、条件として保証会社との契約を求められるケースがあります。保証会社に支払う保証料は、「支払手数料」で経費に計上できます。
保証期間が今年度のみで終了しない場合、今年度分を「支払手数料」で費用計上、来年度以降の分を「前払費用」で資産計上しましょう。前払費用は、月の経過によって「支払手数料」へ少しずつ振り替え、経費となります。
地代/家賃
アパートを建てるために借りた土地の地代や事務所の家賃などは、「地代家賃」の科目で経費に計上できます。例外として、生計を一にしている家族から土地を借りているときは地代を経費計上できません。
青色事業専従者給与
生計を一にしている家族へ給与を支払うときは、原則として経費には計上できません。例外的に、オーナーが青色申告をしており、10室以上のアパートを経営している場合、従業員である家族への給与を経費に計上できます。
この場合、経費に計上する年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署へ提出しましょう。
新聞図書費
アパート経営に関する情報を収集する目的で購入した新聞や雑誌、書籍などは「新聞図書費」として経費に計上できます。
事業への関連がない書籍などは、経費として認められない可能性が高いため注意しましょう。
立ち退き料
アパートの大規模修繕をしなければ倒壊のおそれがあるなど、やむを得ない理由で賃借人に退去してもらうときは立ち退き料を支払うのが一般的です。立ち退き料は、事業目的の達成に必要な支出として経費計上できます。
オーナーの自己都合など、アパート経営の事業目的ではない理由による立ち退き料は経費として認められない可能性があるため注意しましょう。
不動産取得税
不動産取得税は、アパートの取得価格に応じて課税される地方税であり、「租税公課」として経費に計上できます。不動産取得税の計算は、以下のとおりです。
不動産取得税=不動産の固定資産税評価額×3%(軽減税率適用)
不動産の購入後、所有権移転登記をしてから約3カ月~1年後に行政から納付書が送付されるため、記載された期日までに納付しましょう。
登録免許税
アパートを取得したときは、新築であれば所有権保存登記、購入や相続であれば所有権移転登記を法務局へ申請します。
登記申請をするときは、申請書に収入印紙を貼り付けて登録免許税を納付しますが、登録免許税は経費として「租税公課」に計上できます。
印紙税
アパートの売買契約書や工事請負契約書を締結するときには、収入印紙を契約書に貼り付けして納税します。印紙税は、「租税公課」の科目で経費に計上できます。
固定資産税
固定資産税は毎年1月1日時点で所有するアパートの評価額に応じて課税される税金です。固定資産税は「租税公課」として経費に計上できます。
毎年4~5月頃に届く行政からの納税通知書をもとに納税しましょう。
都市計画税
都市計画税は、行政の都市計画をもとに区域内でアパートを所有するオーナーへ課税される税金です。通常、納付は固定資産税とあわせて行われ、「租税公課」で経費に計上します。
アパート経営で経費計上できないもの
アパート経営では、経費に計上できない支出もあるため注意しましょう。具体的には、以下のような支出や納税は経費に計上されません。
経費に計上できないもの
| 経費に計上できないもの | 具体例 |
|---|---|
| 借入金の元金の返済 | アパートを購入するための借入金元金の返済 |
| 修繕積立金 | 大規模修繕のための積立金 |
| 団体信用生命保険特約料 | 個人として団体信用生命保険に加入するときの特約料 |
内容について詳しく解説します。
借入金の元金の返済
借入金の返済は、元金と利息の部分に分かれます。利息の返済は経費に計上できますが、元本を返済した分については経費に計上できません。
借入金は、もともと借入れをしたときに損益計算書の経費項目ではなく貸借対照表の「借入金」で計上しています。元金を返済したときも同様に貸借対照表の「借入金」を減少させるため、経費とはなりません。
修繕積立金
築年数が経っているアパートの場合、大規模な修繕が必要になるケースが多く、そのためにオーナーが積み立てておくのが修繕積立金です。修繕工事がまだ行われていない状態であるため、修繕積立金は経費として計上できません。
一方で、賃貸住宅修繕共済制度を利用すると修繕の積立金を経費として計上できます。賃貸住宅修繕共済は、全国賃貸住宅修繕共済協同組合が提供する共済であり、以下の種類があります。
共済の種類と対象
| 共済の種類 | 対象 |
|---|---|
| 修繕共済 | ・大規模修繕で行われる以下の工事 ①屋根の修繕 ②軒裏の修繕 ③外壁塗装や外壁の修繕 |
| 火災修繕共済 | ・火災や落雷、破裂などによって建物に生じた損害 |
参考:賃貸住宅修繕共済「仕組み図」
共済掛金を経費として計上できるため、大規模修繕に備えて積み立てをしつつ、節税につながるのがメリットです。
対象となる修繕工事が限られているほか、物件についての利用条件もあるため、詳細は以下のページで確認しておきましょう。
団体信用生命保険特約料
団体信用生命保険とは、ローンの契約者が事故や病気で残債を返済できなくなったときに返済義務を免除する制度です。オーナーが個人として団体信用生命保険に加入するときの特約料は、アパート経営に必要な経費とは認められません。
事業の経費ではなく、オーナー個人の保険とみなされるためです。なお、個人でなく法人として団体信用生命保険の特約料を支払うときは、法人の経費に計上できます。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
鳥塚 正人
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





