オーナーチェンジ物件で失敗しないために、危険やリスクを徹底分析
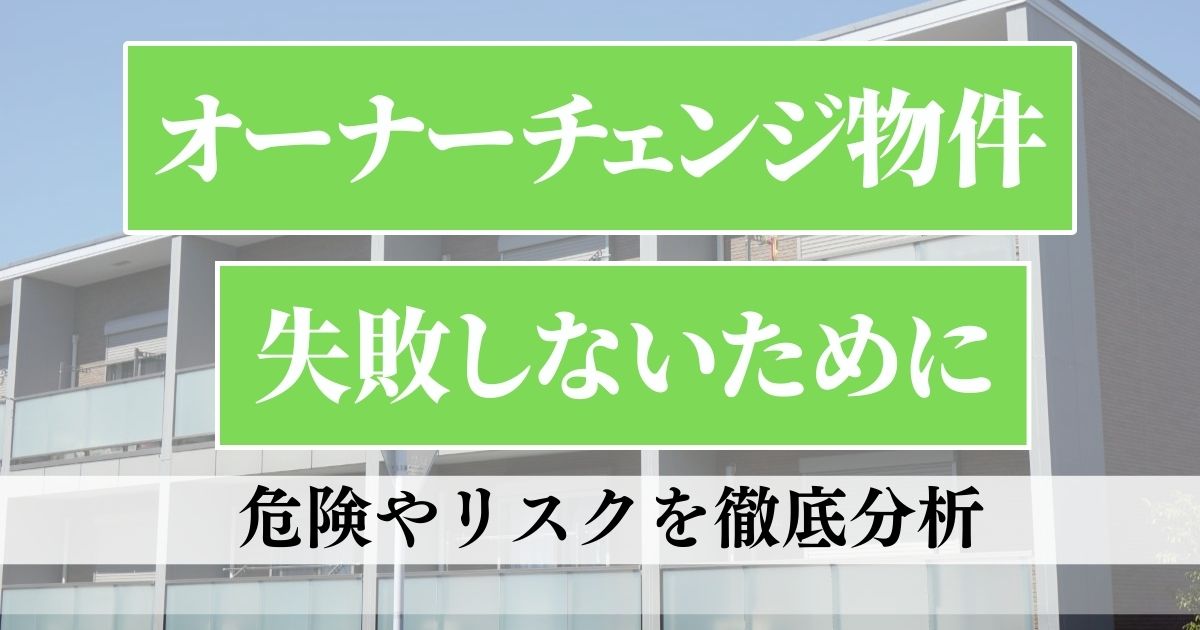
オーナーチェンジの物件はさまざまなメリットがあるものの、危険だともいわれています。
オーナーチェンジ物件が危険な理由と対策を解説します。
この記事の目次
オーナーチェンジの物件は危険なのか
オーナーチェンジの物件は購入後にさまざまな問題が発生する可能性があり、危険だといわれています。そもそもオーナーチェンジ物件とはどのような物件なのでしょうか。
ここではオーナーチェンジ物件の概要や危険な理由と対策などについて、詳しくみていきましょう。
オーナーチェンジ物件とは?
オーナーチェンジ物件とは、すでに入居者がいる状態で売買された物件です。入居者からすると、オーナーが変わることになります。これまでのオーナーであった売主が入居者と締結した賃貸契約はそのまま買主が引き継ぎます。
オーナーチェンジの物件はすでに入居者がいるため、キャッシュフローがはっきりしている点や今後の投資計画を策定しやすいメリットがあります。その反面、物件の状態を把握しづらい点やファミリータイプの部屋だと売却しづらい点などがデメリットとして挙げられます。
ファミリータイプのオーナーチェンジ物件は、ワンルームより利回りが低くなりやすいです。オーナーチェンジ物件の融資で一般的な不動産投資ローンは、審査で収益性が重視されるため、利回りが低いと融資を受けられないケースがあります。現金で購入できる買い手に限定されてしまい、売却のハードルが上がります。
オーナーチェンジ物件は不動産投資が初めてでスタートから家賃収入を得たい人や、空室リスクを事前に回避したい人などにはおすすめです。すでに入居者がいるため金融機関から高評価を受けやすく、有利な条件でローンを組みやすいオーナーチェンジ物件は、実績を持たない不動産投資の初心者には嬉しいでしょう。
空室物件のメリット・デメリット
入居者がいない状態の空室物件はあらかじめ物件の状態を確認できるため、修繕やリフォームの有無といった費用を計画できる点がメリットです。また入居者を自分で審査できます。
反面、入居者がつくまで時間がかかる可能性がある点や入居者募集に費用がかかる点などがデメリットとして考えられます。自分で入居者を見極めたい人や、物件の状態などをあらかじめ確認したい人は空室物件のオーナーとして始めるのがよいでしょう。
オーナーチェンジ物件が危険な理由と対策
オーナーチェンジ物件が危険だといわれている理由として、主に下記の7つが挙げられます。
- 物件の室内の状態が確認できない
- 入居者がどのような人が分からない
- 入居偽装されている可能性もある
- 原状回復費用でトラブルになる可能性がある
- 悪質な入居者を追い出すのが難しい
- 住宅ローンが組めない
- 家賃や契約内容が引き継がれる
ここでは、それぞれの理由について対策も含めて紹介します。
物件の室内の状態が確認できない
オーナーチェンジ物件はすでに入居者がいる状態で権利を引き継ぐため、購入した物件の室内がどのような状態か確認ができません。建てられてから年数がたっている場合などは、修繕の必要がある箇所に気付けない可能性があります。購入後に雨漏りなどが見つかり、高額な修繕費がかかることも多いです。
オーナーチェンジ物件の場合は、入居者から許可を得て、可能な範囲で現地調査を行い、建物の状態や入居者の様子などを実際にみておくとよいでしょう。
入居者がどのような人が分からない
オーナーチェンジ物件は、すでに入居している人がどのような人かを知ることが困難です。問題がある入居者や入居者間でのトラブルを後から知ったとしても、オーナーチェンジ後は買主が対応していかなければなりません。
オーナーチェンジ物件を選ぶ際は入居者リストの内容やトラブルの有無などの情報収集を行いましょう。あらかじめ知っておくことでオーナーチェンジ後にトラブルが発生してもスムーズに対応できます。
入居偽装されている可能性もある
オーナーチェンジ物件の利点はすでに入居者がいる点ですが、売買が有利に進められるよう入居偽装して、あたかも入居者がいるように装うトラブルに巻き込まれる可能性があります。
入居偽装は空き部屋に一時的に人を住まわせて、入居率が高いと思わせる手法で売買後には空き部屋が多い状況に陥ります。
入居偽装をしている物件を見極めるためには、入居者の賃貸契約書をみせてもらったり、実際に物件に足を運んで住んでいる様子を伺ったりするなどして怪しい点がないか確認しましょう。
原状回復費用でトラブルになる可能性がある
入居者が部屋や設備を乱暴に扱っていると、修繕や原状回復に多額の費用がかかってしまい、費用負担を入居者とオーナーどちらで負担するのかトラブルになるケースも往々にあります。
オーナーチェンジ物件では、入居者がどのように部屋を使っているのか確認するのが難しいです。そのため、賃貸契約をよく確認して退去時の原状回復費用の負担についてどのような内容で契約を交わしているのかあらかじめみておきましょう。
悪質な入居者を追い出すのが難しい
すでに入居者がいるオーナーチェンジ物件は、悪質な入居者がいてトラブルが起きていることがあります。
具体的には賃料の滞納や騒音、指定場所以外へのゴミ捨てなどさまざまありますが、入居者をむやみに退去させることはできませんが、賃貸契約で定められた義務やその他法令に反していて、その違反がオーナーとの信頼関係を破綻させる程度である場合は強制的に退去させることが可能です。
悪質な入居者に対しては、注意・警告を繰り返し行ったにもかかわらず従わない場合に退去勧告を行います。悪質な入居者への対応は単独で行わず、管理会社や弁護士などにも相談しながら協力して行うのがよいでしょう。
住宅ローンが組めない
オーナーチェンジ物件は投資目的の建物購入に該当するため、居住用を目的とした建物購入で利用できる住宅ローンは契約できません。
投資目的にもかかわらず住宅ローンを契約した場合、住宅ローン利用した金融機関がその事実を知った時点で、一括返済を求められ、詐欺罪で刑事告訴される可能性があります。オーナーチェンジ物件でローンを活用したい場合は、投資用のローンやアパートローンなどの目的に合った融資を選択しましょう。
家賃や契約内容が引き継がれる
オーナーチェンジ物件は前オーナーと入居者との賃貸契約がそのまま引き継がれるため、家賃や契約内容もオーナーチェンジを理由に変更はできません。
家賃が周辺の物件相場よりも低く、租税負担が上がっている場合は、内容証明郵便による書面や口頭などで入居者との値上げ交渉も可能です。しかし、互いに合意に至らない場合は、契約解除やオーナーチェンジ物件の売却も考えられるでしょう。
オーナーチェンジ物件の事例から学ぶ成功のポイント
オーナーチェンジ物件は危険だといわれ、さまざまな失敗事例がありますが、そこから成功に導くポイントがいくつか挙げられます。ここでは、失敗事例とその原因から成功のポイントをみていきましょう。
失敗事例とその原因
オーナーチェンジ物件は入居者がどのような人なのか、建物がどのような状態なのかを詳細に確認するのが難しいため、さまざまな失敗が発生します。具体的には下記のような失敗事例が挙げられます。
- 入居者の大半がサクラで、短期間に多くの退去者が出た
- 長期入居者が退去後に家賃が大幅に値下がってしまった
- 保証人が不在で、滞納した家賃が回収できなかった
- サブリース物件で途中解約できなかった
失敗の原因としては、入居者や建物の状態をよく確認しなかった点や売買契約にあたって条件などを詳しくみていなかった点などが挙げられます。オーナーチェンジ物件は売買契約を締結する前に、上記の点をよく確認することが成功のポイントといえるでしょう。
そのためには、現地調査をして実際に目の当たりにすることや前オーナーからの聞き取りも重要です。高利回り物件や家賃相場よりも高い賃料を提示しているケースこそ、より慎重に確認しましょう。
物件探しに自信がない場合、信頼できる不動産会社からの購入がおすすめ
オーナーチェンジ物件は入居者や建物の状態、売買契約の内容をよく確認するのが成功のポイントですが、不動産投資の初心者や専門的な知識に自信がない人にとっては見極めが難しいかもしれません。
その場合は、信頼できる不動産会社からオーナーチェンジ物件を購入するのがおすすめです。不動産会社から買い取って再販売しているオーナーチェンジ物件であれば、前オーナーから買い取る際に入居者や建物の状態について詳しく調べた上で買い取っています。
また、ノウハウが蓄積されているため、豊富な物件情報を保有している点もおすすめといえるでしょう。
オーナーチェンジ物件に自分が住みたい場合の手順と注意点
オーナーチェンジ物件に自分が住みたい場合は、空き部屋がすでにあるとすぐに入居が可能です。もし、満室ですぐには住めない状態であれば、まず入居者との賃貸契約を確認しましょう。
賃貸契約には「定期建物賃貸契約」と「普通建物賃貸契約」の2種類があります。定期建物賃貸契約とは、契約期間が定められており、終了すると自動的に契約終了となり入居者は退去する契約です。
一方、普通建物賃貸契約とは定期建物賃貸契約同様、契約期間が定められていますが、入居者が継続して居住を希望すると更新される契約です。
オーナーチェンジ物件は前オーナーと入居者との契約がそのまま引き継がれることから、どちらの契約になっているのか確認します。そして、入居者が退去するまで待てる場合は自然に退去するのを待ちましょう。
更新のタイミングや転勤などで空室ができる可能性があります。しかし、すぐに住みたい場合は入居者に立ち退き料を支払って住む方法もあります。その場合、引っ越し費用のほかに賃料の6カ月〜12カ月分を支払わなければなりません。
ほかにも新居探しの仲介手数料や敷金の不足分が発生することもあります。自分が住む際にはこれらのコストがかかる可能性があることを理解しておきましょう。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
飯野一久
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





