サラリーマンが不動産投資するメリットは?失敗する原因と対策方法を紹介
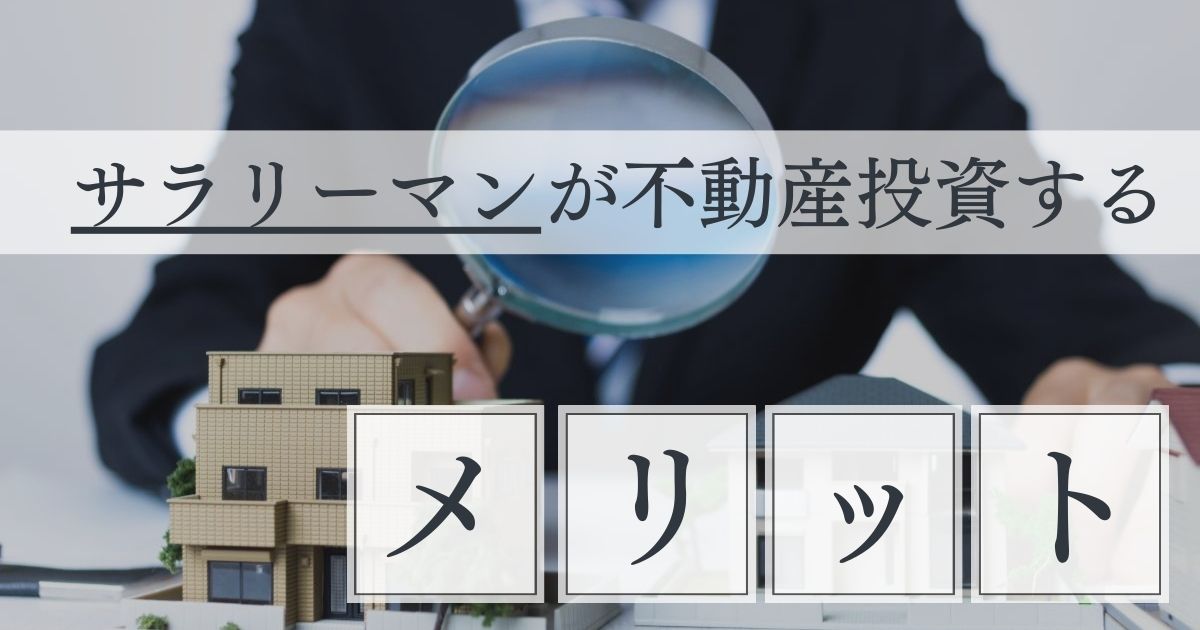
安定した給与収入を得られるサラリーマンは、不動産投資において他の職種よりも有利にスタートできます。金融機関から信頼を得やすく、赤字が出ても給与所得との損益通算により税負担を軽減することが可能です。
副収入として家賃収入を得られる一方で、空室リスクや修繕費を軽視すると大きな損失につながります。サラリーマンが不動産投資をするメリットと、失敗する理由と対処法を紹介するので事前に理解を深めておきましょう。
この記事の目次
サラリーマンが不動産投資するメリット
サラリーマンにとって、不動産投資は副収入の確保や将来の資産形成につながる手段です。給与収入が安定している職業のため、金融機関のローン審査で有利に働く点が大きな魅力といえます。
さらに、不動産投資専用のローンに付帯する団体信用生命保険を活用すれば、生命保険代わりとして家族を経済的に支えることも可能です。
もちろん、投資なのでリスクは伴いますが、サラリーマンの立場を活かすことで安定した運用につながります。まずは、サラリーマンが不動産投資することで得られる4つのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
副収入として家賃収入が得られる
不動産投資の最大の魅力は、家賃収入という安定したキャッシュフローを得られる点です。サラリーマンの給与は基本的に固定給であり、景気の影響を受けにくい一方で、大幅に増えることが少ないといわれています。
不動産投資を始めることで、給与に加えて毎月家賃収入を得ることができ、将来の貯蓄のほか旅行や教育資金といったライフイベントに活用できます。
たとえば、ワンルームマンションの1室を保有していれば、毎月数万円の家賃収入が見込めます。ローンの返済を差し引いても手元に残るお金が生活を支えてくれるでしょう。給与以外に収入源を持つことで経済的な安定性が高まり、将来に対する不安を軽減できます。
長期的な資産形成につながる
不動産投資は長期的な資産形成を目的とする投資手法です。ローンを利用して購入した賃貸物件は、時間の経過とともにローン残債が減少し、将来的には借入を完済することで不動産が手元に残ります。
さらに、老後の生活資金として家賃収入を得続けることができたり、売却してまとまった現金化を図ったりすることも可能です。株式や投資信託のように価格変動が大きい金融商品と比べ、不動産は実際に触れられる実物資産のため、価値が下がりにくい点も安心材料です。
サラリーマンは、家賃収入や給与収入をローン返済に充てながら資産を増やせるため、無理のないペースで資産形成を進められるのは大きなメリットといえるでしょう。
団信を生命保険の代わりにできる
不動産投資ローンは、一般的に「団体信用生命保険(団信)」への加入が必須です。団体信用生命保険とは、ローンを組んだ人が万が一死亡または高度障害状態になった場合に、残りのローンを保険会社が肩代わりしてくれる仕組みです。
つまり、投資家本人が亡くなった場合はローンの返済義務が消滅し、残された家族にはローンのない不動産が遺産として残るのです。これは、生命保険と同じように遺族の生活を保障するための保険といえるでしょう。
子育て世帯や住宅ローンと併用している家庭にとっては大きな安心材料となり、生命保険料を節約することにもつながります。不動産投資を始めることで、資産形成と保障を同時に得られる点は、サラリーマンにとって非常に大きな魅力です。
投資用のローン審査に通りやすい
サラリーマンは安定した給与収入を得られる職業のため、金融機関からの信頼が厚く、不動産投資ローンの審査において有利といえます。
特に勤続年数が長く、大手企業や公務員など安定性の高い職場に勤務している場合は、融資額や条件が優遇されやすい傾向です。これにより、自己資金が少なくても高額な不動産を購入でき、効率的に資産形成を進めることが可能です。
自営業者やフリーランスの場合、収入が不安定とみなされ融資を受けにくいケースも多いため、サラリーマンという立場は大きな強みとなります。また、給与と家賃収入の両方を返済に充てられると評価されることで、ローン返済に余裕が生まれやすい点もメリットです。
サラリーマンが不動産投資で失敗する理由と対処法
不動産投資は、正しい知識と計画で臨めば安定した収入と資産形成が可能です。しかし、十分なリサーチを怠ったり、リスクを過小評価したまま始めたりしてしまうと、思わぬ損失につながるケースも少なくありません。
サラリーマンには本業があり、投資にかけられる時間が限られているため、情報不足や管理会社に任せきりでは失敗の原因になりがちです。サラリーマンが不動産投資で陥りやすい4つの失敗例と、その対処法について詳しく解説します。
相場を確認せず物件を購入してしまった
不動産投資で最も多い失敗の1つが、相場を調べずに高値で物件を購入してしまうケースです。不動産会社から提示された価格が相場とは限らないため、同じエリアの売却価格より割高な条件で購入した場合は、利回りが大幅に下がってしまいます。
結果として、家賃収入でローン返済が賄えず赤字になるリスクが高まります。さらに、将来的に売却する場合でも、購入時より安く手放さざるを得なくなり、資産形成どころか損失を抱える可能性もあるでしょう。
サラリーマンの中には忙しさから業者の提案を鵜呑みにしてしまう人もいますが、自分で市場動向を調べて把握することが大切です。
対処法
物件購入前に必ず周辺エリアの家賃相場や成約事例を調べ、提示された価格が妥当かどうかを確認することが重要です。
国土交通省の不動産情報ライブラリや、民間の不動産ポータルサイトを活用すれば、実際の成約価格や家賃相場を簡単に調べられます。また、複数の不動産会社に相談し、売却の相見積もりを取ることで価格が正しいか判断しやすくなります。
不動産の相場を理解して購入することで、長期的に安定した収益を得られる確率が高まるでしょう。
空室リスクを想定していなかった
「立地が良いからすぐ入居者が見つかるだろう」と安易に考え、空室リスクを軽視してしまうのもよくある失敗例です。いくら好立地の物件であっても、景気の変動や近隣の新築マンションの登場、入居者層の変化などによって空室が発生する可能性があります。
ローン返済中に家賃収入が途絶えると、給与収入から返済を補填しなければならず、生活を圧迫する恐れがあります。空室期間が長引けば長引くほど、資金繰りに追われて精神的な負担も大きくなるでしょう。
対処法
空室リスクを完全にゼロにすることはできませんが、軽減する方法はあります。まずは物件選びの段階で、最寄りの駅や商業施設などを確認して、賃貸需要が見込めるエリアを選ぶことが大切です。
また、学生・単身者・ファミリーなどターゲット層を明確にし、それに合わせた間取りや設備を選びます。さらに、万が一に備えて家賃保証サービスを導入するのもよいでしょう。複数物件を保有してリスク分散を図る戦略も、サラリーマンにとって有効な方法といえます。
毎月の経費や修繕費について考えていなかった
不動産投資を始める際に見落とされがちなのが、物件の維持に必要な経費や修繕費です。表面利回りだけを見て利益が出そうとしてしまうと、管理費・修繕積立金・固定資産税などのランニングコストにより赤字になるケースも少なくありません。
さらに、物件の築年数が経過すれば給湯器やエアコンの交換、外壁補修など突発的な大規模修繕が発生する可能性もあります。それらの費用を見込んでいないと、急な出費に対応できず資金繰りが破綻してしまうリスクがあるのです。
対処法
投資を始める前に「実質利回り」を必ず計算しましょう。実質利回りは、家賃収入からローン返済額、管理費・修繕積立金・固定資産税などを差し引いた後の収益をもとに計算するものです。
また、将来的な修繕に備えて、毎月の家賃収入の一部を修繕積立金として確保しておくことも欠かせません。購入前に過去の修繕履歴や管理組合の修繕計画を確認しておくことで、大規模修繕のタイミングや費用感を把握でき、資金計画に組み込みやすくなります。
不動産会社や管理会社に任せきりにしていた
サラリーマンは本業が忙しいため、不動産投資の運営を全て管理会社や不動産会社に任せてしまうことがあります。
もちろん、専門家に委託することで効率的に運営できますが、完全に任せきりにすると、入居者募集が不十分であったり、修繕費の見積もりが割高であったり、不要な工事を提案されたりといったトラブルにつながるリスクがあります。
また、自身が物件の状況を把握していないと、不動産会社の判断だけで利益を削られてしまう可能性があるため注意が必要です。
対処法
業者に任せる部分と自分で対応する部分のバランスを取ることが大切です。たとえば、管理会社に運営を依頼する場合でも、定期的に収支報告をチェックし、空室率や修繕費の内訳を把握しておきましょう。
また、管理会社を選ぶ際は入居者募集の実績や対応の速さ、サービス内容を比較することで、空室や入居者へのクレームを防げます。さらに、不動産投資に関する知識を深め、物件の収支を細かくシミュレーションすることで業者任せのリスクを大幅に減らせます。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
鈴木 和典
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





