相続したアパートは3年以内に売却しないと税金で損する?特例・控除を解説
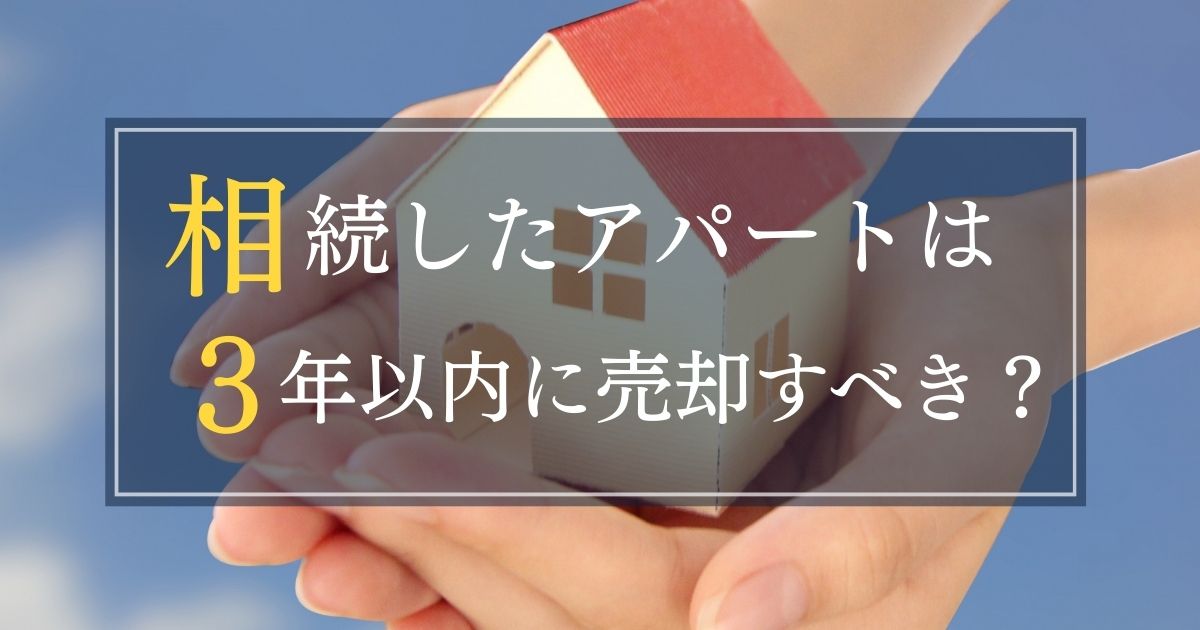
相続したアパートを売却する場合、3年以内に売らないと数百万円単位で税額が増えるリスクがあります。
想定外の支出に見舞われないためにも、「3年以内ルール」の仕組みや、適用できる特例・控除について確認しておきましょう。
この記事の目次
相続したアパートは3年以内に売却しないと税金で損する?
3年以内に売却しないと税金面で損をするといわれる主な理由は、次のとおりです。
- 支払った相続税額の一部を不動産の取得費に加算できなくなる
- 事業用の資産買い替え時の特例が適用できなくなる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
支払った相続税額の一部を不動産の取得費に加算できなくなる
相続したアパートを3年以内に売却すれば利用できる、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を活用すると、支払った相続税のうちの一部を物件取得費に加算できます。つまり、売却益から算出される所得税の節税が可能です。
ただし、この特例を活用できる期限は、相続開始翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日まで、と定められているため、「相続したアパートは3年以内に売却しないと税金で損する」といわれるのです。
事業用の資産買い替え時の特例が適用できなくなる
被相続人が運営していたアパートを相続したものの、そのままで運営継続できないなどの理由から、近隣区域で新しい物件に買い換える場合には、税金を繰り延べできる「事業用の資産を買い換えたときの特例」があります。
具体的には近隣区域で別の物件を購入し、1年以内に新しい物件で事業をリスタートするには、将来に新しく取得した物件を売却するときまで課税を繰り延べできる制度です。
期限がシビアであるものの、すでに居住者がいて相続を機に物件を新しくしたい、といった場合に役立つ制度でしょう。
相続したアパートを3年以内に売却すると使える特例・控除
相続したアパートを売却する際に使える特例や控除にはいくつか種類がありますが、基本的に併用はできません。それぞれの制度の要件や内容を理解しておくと、最適な方法を選べます。
- 相続したアパートを売却だけしたい場合:相続税の取得費加算の特例
- 1億円未満のアパートを売却する場合:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
- 相続した物件を買い替えて1年以内に事業開始する場合:事業用の資産を買い換えたときの特例
相続税の取得費加算の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、「支払った相続税の一部を、物件取得費に加算することで所得税算出時の譲渡所得を軽減し、節税できる制度です。この特例で取得費に相続税を加算する際の、加算額の算出は以下の計算式です。
加算できる相続税額=支払った相続税額×(相続税算出時の相続税評価額÷相続時の取得財産価額+相続時精算課税適用財産価額+純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額)
相続税をすでに支払っている場合、その一部を取得費に含められるため、譲渡所得が減り、結果として所得税や住民税が少なくなるという仕組みです。特に相続税の負担が大きかったケースでは、効果が高いといえるでしょう。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
被相続人が一人で暮らしていた自宅を相続したものの、その後誰も住んでいない空き家を売却した場合に、最大3000万円まで譲渡所得から控除できる制度です(被相続人の居住用財産を売ったときの特例)。
被相続人居住用家屋に認められるための条件
この特例を利用する要件を満たすハードルは、高いのが実情です。しかし、最大3,000万円の控除を受けられるメリットは大きく、該当する場合は積極的に活用すべき制度といえるでしょう。
要件を満たすには、売却する家屋が「被相続人居住用家屋」に該当しなければなりません。その条件は以下のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと(マンションでは不可)
- 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
非常にややこしいですが、アパート全体を1人の故人が所有しており、その1室に故人が住んでいた場合で、かつ他の部屋に誰も住んでいなかった(実質、他の部屋が空き家となっていた)場合は可能ということです。
特例で控除を受けるための条件
上記の条件に加え、制度を実際に使うには以下の要件を満たす必要があります。
- 相続や遺贈(死因贈与も含む)で不動産を取得していること
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
- 他の譲渡特例との併用がないこと
- 親子・夫婦など特別関係者への売却でないこと
- 同一被相続人分では一度だけ利用できること
売却の方法に応じて次の条件も加わります。
- 家+敷地を売却する場合:耐震適合物件であり、相続から売却までの間は誰も使用していないこと
- 敷地のみで売却する場合:取り壊し前後も含め、相続時から売却まで誰も使用していないこと
- 耐震不適合の場合:翌年2月15日までに耐震改修を行い、売却まで誰も住んでいないこと
事業用の資産を買い換えたときの特例
相続したアパートを売却し、新しいアパートや店舗などの事業用物件を購入する場合には、国税庁の「事業用資産の買換え特例」を利用できます。この制度を使うと、売却による譲渡益に対する課税を、新しい物件を売却するときまで繰り延べできる仕組みです。
この特例を利用するための条件は以下のとおりです。
- 売却した資産と買い換えた資産のいずれもが「事業用資産」に該当すること
- 売却から1年以内に新しい資産を事業用に供すること
- 売却した資産の所在地と買い換えた資産が「近隣区域」と認められること
また、売却価格よりも新しい資産の購入価格の方が高い場合には、売却価格に20%をかけた金額を収入金額とみなして譲渡所得を計算します。そのため、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
この制度は将来に課税を繰り延べる仕組みなので、いずれ売却時には課税されますが、資金繰りを有利に進められるという点で、相続アパートを建て替えや買い替えで活用する場合に非常に有効です。
相続したアパートを3年以内に売却するときの注意点
ここまで解説した特例や控除は、すべて利用できる期限や要件が定められています。そのため、ただ「売る」と決めるだけでなく、実際の売却スケジュールや手続きを適切に管理しなければなりません。
相続したアパートを有利に売却するには、以下のような点に注意が必要です。
アパートの所有期間を正しく数える
相続した不動産の所有期間は、自分が相続してからではなく、被相続人(亡くなった人)の保有期間を引き継ぎます。そのため、長期譲渡所得(5年超)か短期譲渡所得(5年以下)かの判定は、被相続人がどれだけ長くその物件を持っていたかで決まります。
また、特例や控除の期限も、相続開始から3年以内、相続税申告期限の翌日から3年以内など、数え方に違いがあるので注意が必要です。誤解すると期限を逃し、節税のチャンスを失ってしまうことになりかねません。
名義変更は早めに行う
アパートを相続したら、登記簿の名義を自分の名前に変更する必要があります。名義変更をしていないと、売却手続き自体が進められません。
また、名義が曖昧なままだと他の相続人とのトラブルにつながることもあります。早めに名義変更を行うことで、スムーズに売却や税務申告ができるようになります。
家賃滞納者がいる場合は適切な対応が必要になる
アパートを相続したときに、入居者が家賃を滞納しているケースもあります。そのままでは売却時に買主から敬遠され、価格が下がってしまうことがあります。
滞納が続く場合には、内容証明郵便で督促したり、賃貸借契約を解除したり、場合によっては明渡訴訟を行うなど、法的手続きを検討しなければならないこともあります。放置せず、早めに専門家に相談することが大切です。
売却時期のスケジュールをきちんと管理する
特例や控除を利用するには、「売却契約」だけでなく「引渡し」まで完了していることが条件となるケースが多いため注意が必要です。相続税の取得費加算や居住用財産の3000万円控除を狙う場合には、売却活動を早めに始める必要があります。
特にアパートは入居者がいるため、売却活動に時間がかかる傾向があります。入居者対応や物件の査定、不動産会社選びを含め、余裕をもってスケジュールを立てることが節税の成否を分けるといえるでしょう。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
鳥塚 正人
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





