老朽化が立ち退きの正当事由に?知っておくべきポイントを解説
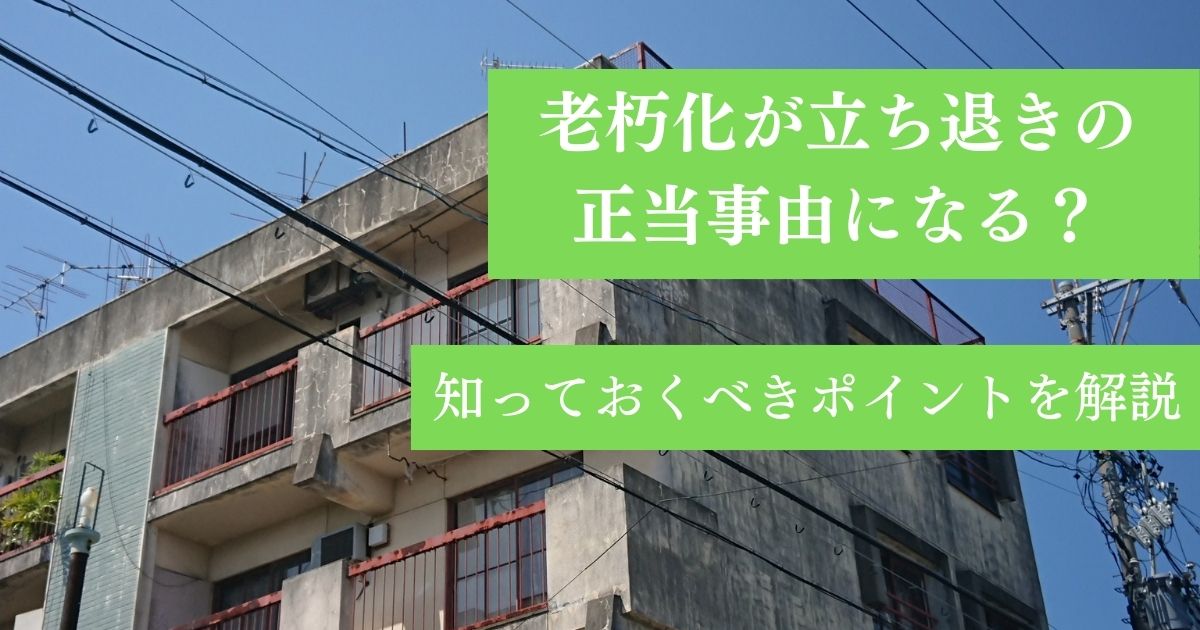
賃貸物件の老朽化などで、入居者に退去をお願いしたくなる場面があります。
しかし大家の希望だけで契約を終了させることはできず、「正当事由」がなければ入居者に退去要請を断られることもあります。
老朽化が立ち退きの正当事由として認められにくい理由や、正当事由を認めやすくさせる方法について解説します。
この記事の目次
賃貸物件の老朽化は立ち退きの正当事由になるのか
アパートの老朽化が正当事由になるかどうかについて、実は絶対的な答えはありません。物件をめぐる状況や入居者側の事情など、複数の要素を総合した上で判断されます。
ここでは、老朽化を理由にした立ち退きが認められる条件や注意点について解説します。
賃貸契約の更新拒絶や解約には、事前の通知が必要
大家側から入居者に対して契約の更新を断ったり解約を申し入れたりする場合は、契約満了日の少なくとも6カ月前までに通知しなければなりません。
例えば、契約が翌年の3月末で満了する場合、遅くとも前年の9月末までには入居者に書面などで通知する必要があります。もしこの期間を過ぎてしまえば、自動的に契約は更新され、次の契約期間中は立ち退きを求められなくなります。
更新の拒絶や解約に正当事由が必要な理由
大家が入居者に退去を求める場合、なぜ法律で定められた「正当事由」が必要なのでしょうか。
それは、この制限がなければ大家の都合だけで契約を打ち切ることが可能になり、入居者が突然住まいを失ってしまうからです。日本の法律では、入居者保護のために大家側の権利行使を制限し、お互いの利益のバランスをとっています。
正当事由かどうかを判断する際には、例えば次のような要素が考慮されます。
- 大家自身が土地・建物を使用する必要性
- 入居者がその物件を必要としている事情
- 賃貸借契約の状況(家賃滞納やトラブルの有無)
- 物件の空室状況
- 建物の老朽化の度合い
- 大家から立ち退き料の申し出があるか
つまり、大家の事情だけでなく、入居者側の事情も必ずセットで比較されるということです。たとえ大家側に賃貸業を辞めたい妥当な理由があっても、入居者が高齢で引越しが困難な場合などは、正当事由が弱まることもあります。
逆に言えば、これらの要素をしっかり揃え、正当事由が十分にあると認められれば、契約終了が法的に認められる可能性が高まります。
参考:借地借家法第28条 | 建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件
老朽化だけでは正当事由になりにくい
「建物が古くなってきたから、そろそろ退去してもらおう」。大家としては自然な発想ですが、老朽化は正当事由を判断する要素の1つに過ぎず、それだけでは正当事由になりにくいのが実情です。
実際の裁判で大家が築50年以上の住宅の明け渡しを請求したものの、老朽化による建て替えの必要性が低いと判断され、大家側の正当事由が認められなかった事例があります(東京地裁令和元年12月12日判決)。
ただし、老朽化に加えて次のような事情があれば、正当事由は強まります。
- 雨漏りや配管劣化など、安全性・衛生面に深刻な問題がある
- 耐震基準を満たさず、地震で倒壊する危険が高い
- 立ち退き料を提示して、入居者の負担を軽減しようとしている
例えば、築45年以上のアパートで、大家が老朽化を理由に解約を申し入れた裁判がありました。
建物の取り壊しの必要性自体は認められましたが、入居者に家賃滞納などの落ち度がなかったため、裁判所は立ち退き料100万円の支払いを条件として入居者に退去を命じています(東京地裁令和2年2月18日判決)。
大家としては、老朽化=即立ち退きと考えるのではなく、他の事情と組み合わせて正当事由を強くするという考え方が必要です。
参考:一般財団法人不動産適正取引推進機構 | RETIO判例検索システム
大家からの退去の要請は断れるのか
大家が入居者に退去を求めても、正当事由がなければ入居者は退去を断れます。入居者は、借地借家法によって保護されており、大家の一方的な都合だけで立ち退きを強制することはできないためです。
例えば「建物が古くなって、入居率が下がってきたから」「取り壊して自宅を建てたいから」といった理由だけでは正当事由としては弱いと判断されやすいでしょう。
正当事由が十分でない場合は、立ち退き料を提示して、入居者の引越し費用や生活への影響を軽減するよう努めるのが一般的です。
ただし、立ち退き料は必ず支払う義務があるわけではなく、正当事由が強ければ発生しないこともあります。そのため、支払わなくてもよいと考える大家も実際に存在します。
立ち退き要請をする際は、
- 法的に正当と認められる理由があるか
- 立ち退き料の有無や金額が妥当か
を事前に整理してから、正式に入居者に伝えましょう。
老朽化したアパートからの立ち退きを依頼する流れ・注意点
入居者に老朽化したアパートからの立ち退きを依頼する流れや注意点を解説します。
立ち退きの流れは、次のようになります。
- 入居者に賃貸借契約の解約を申し入れる
- 立ち退き条件の交渉を始める
- 退去条件について合意を交わす
- 明け渡し日を迎える
立ち退き費用の相場や立ち退き料の内訳
立ち退き料は、入居者が新居へ移るための実費負担に加え、慰謝料などを含めた金額として提示するのが一般的です。
立ち退き料の内訳は、次のようになります。
(引越し先との家賃差額×12カ月~24カ月)+新居契約費用+引越し代+慰謝料
現在の家賃が8万円で、家賃10万円の物件に引越す場合の、内訳と目安金額の一例は以下の通りです(消費税は考慮していません)。
| 内訳 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 引越し先との家賃の差額2万円×1年分 | 24万円 | |
| 敷金(2カ月分) | 16万円 | 新居契約時に必要 |
| 礼金(1カ月分) | 8万円 | 地域によって異なる |
| 仲介手数料(1カ月分) | 8万円 | |
| 引越し代 | 10万円 | 時期・距離で変動する |
| 慰謝料 | 10万円 | 精神的負担・生活が変わることへの補償 |
| 合計 | 76万円 |
立ち退き料はあくまで交渉ベースで決まるため、入居者の個別の状況によっては、金額が大幅に変わることもあります。
立ち退き交渉の際のポイント
立ち退き交渉では、感情的な対立を避けつつ法的に正しい手続きを進めることが円滑な解決につながります。
ここでは、大家がスムーズに立ち退きを進めるためのポイントを整理します。
1.事前に綿密なプランを立てる
交渉に入る前に、立ち退きの理由や立ち退きを求めるタイミング、立ち退き料の予算と根拠などを整理しておきましょう。
想定される質問や反論に対する回答も準備しておくと、交渉がスムーズに進みます。
2.立ち退きを求める理由を具体的に伝える
「老朽化による建て替え」や「資金難により、これ以上の賃貸経営が困難になった」など、立ち退きを求める理由は具体的かつ正確に説明することが大切です。曖昧な説明では、入居者が納得しづらくなります。
例えば「老朽化が進行しており、調査の結果、このままでは倒壊の危険があることが判明したため」と調査書を添付してお願いすれば、入居者の理解を得やすいでしょう。
3.合意内容は書面化する
口約束だけではトラブルのもとになります。退去日や立退料の額など、合意内容は必ず書面にして双方が署名・押印しましょう。誤解による紛争を防ぐためにも重要です。
立ち退き交渉をスムーズにする方法
次は、大家がスムーズに立ち退き交渉を進めるための具体的な方法をご紹介します。
立ち退き交渉が上手くいかない場合の対策
立ち退き交渉は、大家と入居者の立場や事情がぶつかる場面が多く、思うように進まないことも珍しくありません。
そのような場合は、次の2点を確認してください。
1.入居者の事情を聞き取り、適切な対策をとる
交渉を進めるためには、入居者が、なぜ引越しを望まないのかを理解することが必要です。
例えば、
- 新しい住まいを探す時間がない
- 引越し費用の負担が大きい
- 長く住み慣れた環境を離れたくない
といった理由はよくあるケースです。
特に高齢者の場合、体力的な負担や住み替え先探しが難航する不安もあるため、十分な配慮が必要です。
事情を把握した上で、例えば次のような対応を検討しましょう。
- 他に所有している物件の空室に入居してもらう
- 不動産会社や引越し会社を紹介する
- 立ち退き料の一部を前払いする
入居者の負担を減らす姿勢を見せることで、交渉に応じてもらいやすくなります。
2.適正な立ち退き料を提案する
契約違反がない入居者に退去をお願いする場合、立ち退き料はほぼ必須です。新居の敷金・礼金・仲介手数料や引越し代などの実費補償に加え、慰謝料も含めて提示すると受け入れられやすくなります。
事前にできる立ち退き拒否の回避策
建て替えや自己使用を予定している場合は、あらかじめ普通借家契約から「定期借家契約」に切り替えておくと、立ち退き時のトラブルを防ぎやすくなります。
定期借家契約とは、あらかじめ契約で定めた期間が満了すると、自動更新されずに契約が終了する仕組みの賃貸借契約です。
このため、契約終了後の明け渡しがスムーズになり、立ち退き料も不要となる点がメリットです。
ただし、次のような注意点があります。
- 平成12年3月1日より前に締結された賃貸借契約は、定期借家契約に切り替えられない
- 契約時に「この賃貸借は更新がなく、期間満了で終了する」旨を、契約書とは別の書面で入居者に説明する必要がある
- 契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6カ月前までに契約終了を通知しなければならない
このように、定期借家契約は普通借家契約と異なるルールがあるため、定期借家契約に実績のある不動産会社や専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です。
また、定期借家契約は入居希望者が少ない傾向があるため、家賃を相場より下げることも検討しましょう。
参考:国土交通省|定期借家制度
スムーズに立ち退いてもらうには不動産会社への相談も有効
立ち退き交渉を進めるには、法律や契約内容を正しく理解するだけでなく、入居者への細やかな配慮が欠かせません。大家自身が全て自力でやろうとすると、交渉が行き詰まったり感情的な対立を招いたりするリスクがあります。
不動産会社に相談すれば、過去の事例をもとに適正な立ち退き料や交渉の進め方についてアドバイスを受けられます。
また、引越し先物件の紹介や引越し会社の手配など、入居者の負担を減らすサポートが可能な不動産会社もあります。交渉が不安な場合や、できるだけ円満に話をまとめたい場合は、早めに信頼できる不動産会社へ相談するほうが安心です。
立ち退きが上手くいかない場合は売却という選択肢も
立ち退き交渉が上手くいかない場合、一度立ち止まって「売却」という選択肢を検討するのも1つの案です。
特に、老朽化が進んだアパートでは、次の2つの方法が現実的な選択肢になります。
- 入居者がいるまま、オーナーチェンジ物件として売却する
- 不動産買取会社に直接売却する
以下で、それぞれの特徴と注意点を解説します。
入居者がいるままオーナーチェンジ物件として売却する
「オーナーチェンジ」とは、買主が入居者との契約をそのまま引き継ぐ状態で物件を売却する方法です。
オーナーにとっては、立ち退き交渉から撤退して不動産を現金化できるのがメリットです。買主にとっても、購入後すぐに家賃収入が得られるため、投資用物件として魅力があります。
ただし一般的なマンション売却よりも売却価格が下がります。
不動産買取会社に直接売却する
「買取」とは、仲介を通さず不動産会社が直接物件を買い取る方法です。買主を探さなくてよいため、契約から現金化までのスピードが早い点がメリットです。また入居者がいたり、老朽化していても買い取ってもらえます。仲介ではないため仲介手数料は不要です。
一方で、不動産買取会社は再販して利益を得る必要があるため、仲介売却と比べると提示される金額は低いのが一般的です。「できるだけ早く手放したい」場合に向いている方法といえるでしょう。
建物が老朽化しただけでは、立ち退きの正当事由としては認められないのが実情です。そのため、立ち退き交渉は入居者の事情や感情に配慮しながら慎重に進めましょう。
まずは、契約内容や物件の状態を整理し、信頼できる不動産会社や専門家に早めに相談してみてください。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
飯野一久
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





