一棟マンション経営の費用はいくら?安く抑える方法や維持費を解説
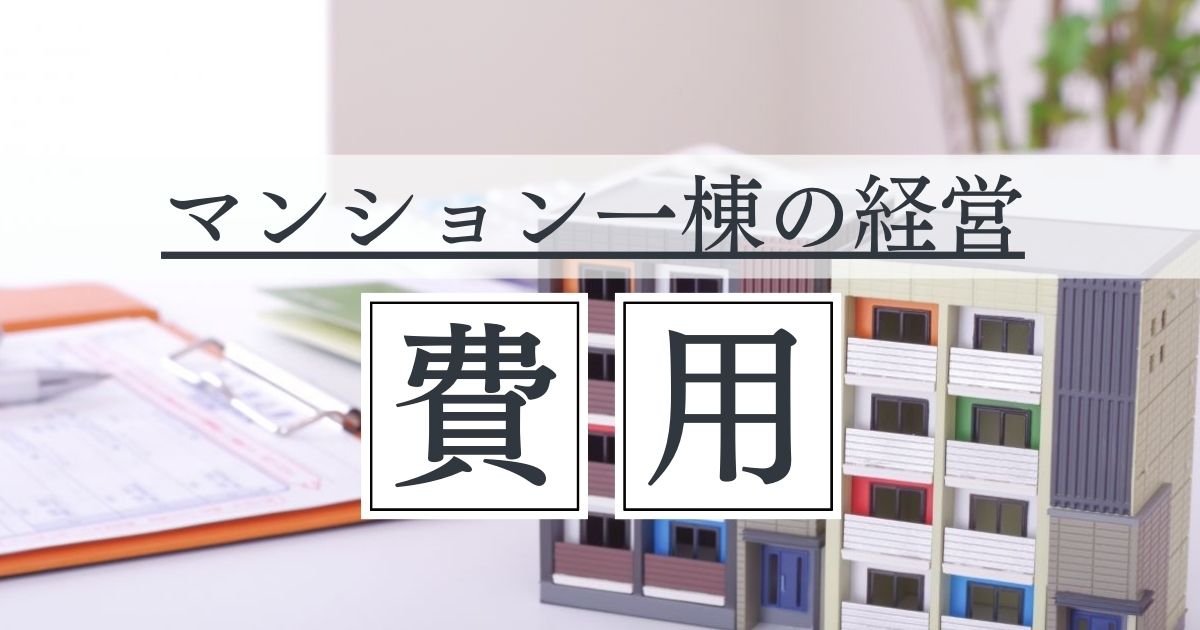
一棟マンション経営では、購入費用だけで1億円規模の費用を要します。
さらに、税金やローンの利息、管理費や修繕積立金、保険料といった毎月の支払いも無視できません。
無駄な支出を抑えて長期的に安定した収益を確保するために、経営で必要な費用と安く抑えるためのポイントを解説します。
この記事の目次
一棟マンション経営を始めるための初期費用
はじめに、一棟マンション経営を始めるために必要となる初期費用として、マンションの購入費用や建築費用について解説します。
マンションの購入費用
前提として、一棟マンションの購入費用はエリアによって大きく異なります。
首都圏と地方で違うのはもちろんのこと、駅からの距離や周辺施設などによっても変動する点に注意が必要です。
その上で今回は購入費用の目安として、首都圏にあるマンション一棟の価格をご紹介します。
| エリア | 一棟マンションの相場 |
|---|---|
| 東京23区 | 2.5億円~4億円 ※東京23区の中でも特に千代田区・港区・中央区・渋谷区・新宿区5区の相場が高め |
| 東京23区外 | 2億円~2.5億円 |
| 神奈川県 横浜・川崎エリア | 2億円~2.5億円 |
| 神奈川県 横浜・川崎エリア以外 | 2億円前後 ※近年、延床単価は構造に関係なく上昇傾向にあります |
| 千葉県 | 2億円台前半 |
| 埼玉県 | 2億円~2.5億円 |
小規模なマンションや築古物件であれば、一棟でも1億円台で購入することも可能です。
しかしながら、首都圏で一棟マンションを購入する場合は、2億円程度はかかると考えておくとよいでしょう。
マンションを建築する費用
国土交通省による資料「建築着工統計調査」の中で、物件の建て方および構造別の工事費予定額が公表されています。
同調査結果から、構造別の1戸および1㎡あたり工事費予定額を紹介します。
| 構造(建て方:共同住宅) | 1戸あたり工事費予定額(全国値※建築着工統計調査を参考) | 1㎡あたり工事費予定額(全国値※建築着工統計調査を参考) |
|---|---|---|
| 木造 | 734万円 | 21万円 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2,084万円 | 33万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 1,824万円 | 33万円 |
| 鉄骨造 | 1,717万円 | 32万円 |
| コンクリートブロック造 | 773万円 | 24万円 |
| その他 | 1,148万円 | 26万円 |
出典:建築着工統計調査-住宅着工統計-2024年-第34表|国土交通省
1㎡あたりの金額が最も安価なのは木造で、高価な鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄筋コンクリート造と比較すると、12万円もの差があることが分かります。
そのため、マンション建築にかかる費用は、物件の構造によって大きく左右されるといえるでしょう。
一棟マンションの取得費以外にかかる費用
一棟マンション経営を始めるためには、物件自体の購入費以外にもさまざまな付随費用が発生します。
一棟マンションの取得費以外にかかる費用について詳しく見ていきましょう。
税金
一棟マンションに限らず、不動産の購入時には以下の税金の支払いが必要です。
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
それぞれの税金の概要と、金額の目安について解説します。
印紙税
印紙税とは契約書や領収書などに課税される税金です。印紙税の課税対象となる文書は印紙税法で明確に定められています。
印紙税の額は課税文書の種類や契約金額ごとに定められており、不動産売買契約書にかかる印紙税の額は以下の通りです。
| 記載された契約金額 | 原則的な税額 | 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される場合の税額 (印紙税の軽減措置適用) |
|---|---|---|
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 非課税 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | >10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 以降省略 | ||
出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
対象となる文書に税額分の収入印紙を貼付することで、印紙税を納付したとみなされます。
登録免許税
登録免許税は、不動産の場合は登記や登録などに課税される税金です。一棟マンションの購入後に行う不動産登記では登録免許税の納付が必要です。
登録免許税の税額は登記の種類ごとに定められています。一棟マンション購入時にかかる登録免許税は以下の通りです。
| 購入する不動産の種類 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(居住用の家屋のみ適用) |
|---|---|---|---|
| 土地 | 不動産の価額 | 2% | 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は1.5% |
| 新築マンション (所有権保存登記) |
不動産の価額 | 0.4% | 自身の居住用で、令和9年3月31日までに登記を行う場合は0.15% |
| 中古マンション (所有権移転登記) |
不動産の価額 | 2% | 自身の居住用で、令和9年3月31日までに登記を行う場合は0.3% |
出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
軽減税率は住宅用の不動産にのみ適用されます。投資用にマンション一棟を取得するケースでは軽減措置は適用されません。
不動産取得税
不動産取得税とは不動産を取得した人に課税される税金です。都道府県から届く「納税通知書」で金額を確認できます。
不動産取得税は「不動産の課税標準額 × 税率」で計算します。税率は以下の通りです。
- 土地:3%
- 住宅用の家屋:3%
- 住宅用でない家屋:4%
マンション経営を目的とした不動産取得の場合、住宅用でない家屋に該当します。そのため土地部分の税率は3%、建物部分の税率は4%となります。
なお、税率は年度によって変わる可能性があるため必ず最新情報をご確認ください。
日割清算金
不動産売買における日割清算金とは、以下の費用を日割りで計算したものです。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 管理会社に支払う管理費や修繕積立金
固定資産税はその年の1月1日の所有者が納税義務を負います。しかし、不動産を年の途中で手放した場合に、前の所有者が1年分を全額支払うことに納得できない方もいるでしょう。
したがって、その年の固定資産税を日割りした金額を、買主から売主に支払うのが一般的です。
管理費や修繕積立金も同じ考え方です。月の途中で売買が成立した場合、管理費など月額を日割りで計算して買主から売主に支払います。
固定資産税や管理費の金額、売買成立のタイミングによって費用は異なりますが、一般的に数千円~数万円程度です。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産売買が成立した際に仲介を担当した不動産会社へ支払う手数料のことです。
売買取引における仲介手数料の上限額は以下のように定められています。
| 物件の売却価格 | 料率 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% |
| 200万円超400万円以下の部分 | 4.4% |
| 400万円超の部分 | 3.3% |
出典:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ-売買取引の仲介手数料の上限額」
たとえば、一棟マンションの物件価格が2億円だった場合、仲介手数料の上限は以下のようになります。
(2億円 × 3%+ 6万円)+消費税(10%)=666.6万円
仲介手数料の料率は上述した上限どおりに設定されているため、上回る金額を提示された場合は不動産会社の担当者に確認してみましょう。
住宅ローン関連
住宅ローン関連の費用としては以下のようなものが発生します。
- ローン手数料(事務手数料、融資手数料とも呼ばれる)
- ローン保証料
- ローン契約書に貼付する印紙税
- 登録免許税(抵当権を設定する場合)
- 団体信用生命保険料
住宅ローン関連費用の目安は、借入総額の3〜8%程度です。
保険料
一棟マンションの経営に際して発生する保険料として以下の例が挙げられます。
- 地震保険
- 火災保険
- 瑕疵保険(住宅の瑕疵が発生した場合、補修費用などを補償する保険)
なお、地震保険単体での契約は基本的にできません。地震保険に加入する場合は火災保険との付帯契約になるのが原則です。
一棟10戸程度のマンションの場合、火災保険と地震保険を合わせて加入しても年間の費用は8〜13万円程度です。
一棟マンションの経営に必要な維持費
不動産賃貸では物件の購入費だけでなく、維持費として毎月さまざまな経費が発生します。
以下では、一棟マンションの経営で必要になる経費の例をご紹介します。
管理費
マンション経営における管理費とは、共用部分の維持・管理にかかる費用の総称です。管理費に該当する費用として以下の例が挙げられます。
- 廊下、階段、エントランスなど共用部分の光熱費
- 点検・メンテナンス費
- 電球、掃除道具、事務用品など消耗品費
共用部分は入居者ではなくオーナー側が管理、メンテナンスする必要があります。
修繕積立金
修繕積立金とは大規模修繕工事に向けて毎月積み立てるお金です。
国土交通省の資料では、修繕積立金の月平均額は以下のように公表されています。
| 地上階数および延床面積 | 月平均額(1㎡あたり) | |
|---|---|---|
| 20階未満 | 5,000㎡未満 | 335円 |
| 5,000㎡以上1万㎡未満 | 252円 | |
| 1万㎡以上2万㎡未満 | 271円 | |
| 2万㎡以上 | 255円 | |
| 20階以上 | 338円 | |
出典:日本経済新聞「マンションの修繕積立金、目安は国交省の改訂指針」
管理会社の委託費用
一棟マンションに限らず、不動産投資では物件の管理業務を不動産管理会社に委託することが可能です。
管理会社に支払う委託費用は、家賃収入の5%前後といわれています。対応する内容は管理会社によって異なるため、利用する際はサービス内容や利用金額を確認しましょう。
ローン利息
一棟マンションの購入に際してローンを利用した場合は、ローン利息の支払いが必要です。
一棟マンションを2億円で購入し、金利3%の投資ローンを組んだ場合は以下の通りです。
- 年間利息:2億円×3%=600万円
- 月額利息:600万円÷12ヵ月=50万円
不動産投資ローンの金利は年2〜5%が目安となります。ローン残高が多いほど支払う利息は高額になるため注意が必要です。
一棟マンションの経営費用を安く抑えるポイント
最後に、一棟マンションの経営費用を安く抑えるポイントを3つご紹介します。
できるだけ金利が安いローンを探す
一棟マンションの購入時にローンを利用するのであれば、できるだけ金利が安いローンを探しましょう。ローンの金利が高いほど毎月の利息支払い額が高くなり、ランニングコストの負担が重くなるからです。
一棟マンション経営では高額な不動産投資ローンを組むケースが多いため、金利が0.1%違うだけでも利息額が大きく変わります。
借入額を2億円として、金利が0.1%上昇したときの利息額の差は以下の通りです。
【金利が2.5%から2.6%に上昇した場合】
- 年間利息:5,000,000円 → 5,200,000円(差額:20万円)
- 月額利息:416,667円 → 433,333円
金利が0.1%違うだけで、年間20万円前後の利息差が生じます。毎月の返済負担を抑えるためにも、なるべく金利が低いローンを利用するのが理想です。
保険料を一括で支払うようにする
保険料は一般的に月払いより年払いの方が安く済みます。そのため、保険料を抑えるという意味では、保険料を一括で支払う方法が効果的です。
ただし、マンション一棟経営では戸数が多い分保険料は高額になりがちです。年払いではまとまった資金が必要となるため、無理のない範囲で一括払いを行いましょう。
国の特例や自治体の補助金制度を利用する
国の特例や自治体の補助金制度を利用することで、マンション経営にかかる経費の負担を減らせる可能性があります。
たとえば、国土交通省では子育てに配慮した賃貸マンションの新築・改修を支援する「子育て支援型共同住宅推進事業」を令和8年2月まで実施しています。
具体的な補助・支援内容は以下の通りです。
- バルコニーや窓の手すりの設置:一戸あたり最大100万円補助
- 居住者などとの交流を促す取り組み:一棟あたり最大500万円補助
- 宅配ボックスの設置工事:子育て世帯の入居率に応じて最大50万円補助
補助金制度は適用条件や補助金額が自治体によって異なるため、まずはどのような制度が利用できるのか調べてみるのが良いでしょう。
出典:国土交通省「住宅:子育て支援型共同住宅推進事業について」
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
鈴木 和典
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





