築30年のアパートはいくらで売却できる?賃貸経営を続けるリスクも紹介
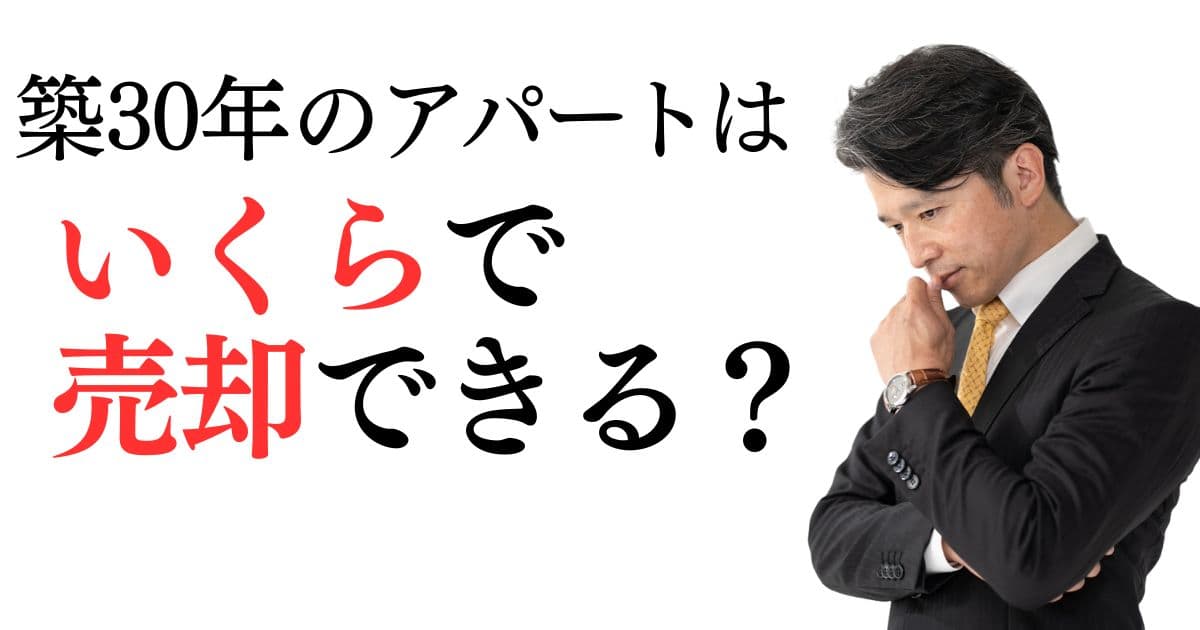
国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査」によると、アパートを含む民間賃貸住宅の平均築年数は17.5年です。
建築時期が昭和60年〜平成6年のアパートの比率は15.4%と多く、遅くとも2024年には築30年を迎えます。
計画修繕やリノベーションを行う余裕がなく、出口戦略として売却を検討している方もいるでしょう。
しかし、アパートやマンションの売却価格は、築30年を超えると大きく下落するといわれています。
本記事では、築30年のアパートの売却相場や、築30年を超えてもアパート経営を続けるリスクを紹介します。
この記事の目次
築30年のアパートの売却相場は?築31~35年から大幅に下落する?
アパートやマンションは、築年数が経過するにつれて資産価値が低下し、売却価格が下がっていきます。
特に下落幅が大きいとされているのが、築30年を超えた物件です。
以下の表は、東日本不動産流通機構の「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(出典2023年)」より、首都圏にある中古マンションの成約価格を築年数別にまとめたものです。
| 築年数 | 成約価格 |
|---|---|
| 築0~5年 | 7,077万円 |
| 築6~10年 | 6,655万円 |
| 築11~15年 | 5,932万円 |
| 築16~20年 | 5,509万円 |
| 築21~25年 | 4,887万円 |
| 築26~30年 | 3,344万円 |
| 築31~35年 | 2,303万円 |
| 築36~40年 | 2,672万円 |
| 築41年~ | 2,260万円 |
上記の表では築26~30年の中古マンションは、平均すると3,344万円で取引されているのに対し、築31~35年になると平均2,303万円に下落しています。
こういった傾向は中古マンションだけでなく、築年数が経過したアパートにも同様に見られます。
出口戦略としての売却を検討している場合は、できるだけ早く不動産会社に相談するとよいでしょう。
築30年を超えたアパートの売却価格が低くなる理由
築30年を超えると、アパートの売却価格が下落する理由は主に以下の3つです。
- 建物の耐用年数が経過しているから
- 入居希望者が減り、空室リスクが増大するから
- 買主が不動産投資ローンを組みにくいから
それぞれ詳しく見ていきましょう。
建物の耐用年数が経過しているから
アパートやマンションなどの不動産は、減価償却資産(償却資産)に含まれ、時間が経過するにつれて価値が目減りする資産です。
減価償却では、資産の取得にかかった金額を使用できる期間に応じて分割し、経費として計上ができます。
この使用できる期間のことを法定耐用年数といいますが、アパートを含む建物の耐用年数は、構造や用途によってさまざまです。
主に住宅用に用いられる建物の耐用年数は、以下の通り財務省が表で分かりやすくまとめています。
| 建物の構造 | 耐用年数 | |
|---|---|---|
| 木骨モルタル造 | 20年 | |
| 木造 合成樹脂造 |
22年 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
47年 | |
| れんが造 石造 ブロック造 |
38年 | |
| 金属造 | 軽量鉄骨(骨格材が3mm以下のもの) | 19年 |
| 軽量鉄骨(骨格材が3mmを超え、4mm以下のもの) | 27年 | |
| 重量鉄骨(骨格材が4mmを超えるもの) | 34年 | |
アパートの構造が木造または鉄骨造(一部)の場合、築30年を超えると耐用年数を過ぎるため、投資物件としての価値は下がりやすくなります。
耐用年数を超えても建物が使えなくなるわけではありませんが、投資物件としては買主から敬遠されやすくなるでしょう。
ちなみに、土地は時間が経過しても劣化しないので減価償却資産には該当しません。
入居希望者が減り、空室リスクが増大するから
築年数が経過した賃貸物件は、建物や設備の老朽化などの理由から、入居希望者が減少し空室率が高くなります。
実際に、国土交通省が行った調査でもマンションの空室率を建物の完成年次別に見ると、築年数が経っているアパートほど空室の割合が大きいという結果が出ています。
下記は、0%が空戸なし、空室戸数(3カ月以上)を0%超~20%または20%超として、空室戸数の割合をまとめた表です。
| 完成年次 | 空室戸数(3カ月以上)の割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20%超 | 0%超~20% | 0% | 不明 | |
| 1984年以前 | 2.9% | 56.8% | 32.1% | 8.1% |
| 1985~1994年 | 0% | 41.6% | 48.2% | 10.1% |
| 1995~2004年 | 0.7% | 31.3% | 60% | 8% |
| 2005~2014年 | 0% | 20.4% | 67.4% | 12.2% |
| 2015年以降 | 0.6% | 16.8% | 71.3% | 11.4% |
国土交通省「令和5年度マンション総合調査」より
表のとおり築30年超のアパートは空室率(0%超~20%)の割合が高く、安定して家賃収入を得られないリスクが想定されることから、売却価格が低くなる傾向にあります。
買主が不動産投資ローンを組みにくいから
築30年を超えるアパートは、買主が不動産投資ローンを組みにくく、購入資金を調達しづらいという問題点もあります。
一般的に不動産投資ローンの審査基準は住宅ローンよりも厳しく、法定耐用年数から築年数を差し引いた期間を融資期間に設定するからです。
たとえば、重量鉄骨造のアパートの耐用年数は34年ですが、築30年のアパートの場合、差し引き4年間しか融資を受けられません。
融資期間が短いと、月々の返済額が大きく増加するため、買主にとってはローンが組みにくくなります。
また、築年数が法定耐用年数を上回っている場合は、ローンを断られるケースもあるようです。
このように築年数が経過したアパートは、さまざまな条件から売れにくくなり、売却価格も低下します。
アパートの売却を検討している方は、賃貸物件の取扱実績が豊富な不動産会社に相談しましょう。
築30年を超えてアパート経営を続けるリスク
アパートの築年数が経過し、そろそろ売却すべきか迷っている方も多いでしょう。
ここでは、築30年を超えてアパート経営を続けるリスクを3つ紹介します。
- 計画修繕やリノベーションが必要になり、支出が増える
- 建物や設備が老朽化し、入居者とのトラブルが増える
- 木造や鉄筋造の場合、減価償却が終わり税負担が増える
それぞれ詳しく解説していきます。
計画修繕やリノベーションが必要になり、支出が増える
アパートやマンションは、築年数が経つと外観の劣化などが進みます。
経年劣化を放置して賃貸経営を続けると、周辺の物件と比べて競争力が低下し、入居率の低下や家賃収入の減少につながるおそれがあります。
築30年を超えてもアパート経営を続ける場合は、毎年の日常点検に加え、定期的な計画修繕やリノベーションが必要です。
たとえば、屋根や屋上防水、外壁などは10年、浴室・キッチンなどの設備は15年を目安として、計画的に補修や修繕を実施するとよいでしょう。
| 場所 | 修繕が必要な周期(目安) | |
|---|---|---|
| 建物 | 屋根・屋上(防水塗装) | 10年 |
| 外壁(塗装・シーリング) | 10年 | |
| 鉄部・非鉄部(塗装) | 10年 | |
| 設備 | 給湯・風呂釡 | 10年 |
| エアコン | 10年 | |
| 浴室設備 | 15年 | |
| 厨房設備 | 15年 | |
| 洗面化粧台 | 15年 | |
| トイレ | 15年 | |
しかし、計画修繕やリノベーションには多額の費用がかかります。
家賃収入が減少傾向にある築30年のアパートの場合、修繕費用などの負担が重くなり、損益分岐点(売上と経費が等しいこと)を下回るケースも少なくありません。
赤字経営が続く場合は、出口戦略としてアパートの売却を検討するのも一つの方法です。
建物や設備が老朽化し、入居者とのトラブルが増える
建物や設備が老朽化すると、入居者とのトラブルが増加する傾向にあります。
国土交通省が行った「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」によると、入居者とのトラブルのうち、2番目に多いのが「入居者からの修繕などの要望対応に手間やお金がかかる(18.9%)」です。
そのため、築30年を超えるアパートは、入居者とのトラブル対応に追われ、管理コストが増大するというリスクがあります。
木造や鉄筋造の場合、減価償却が終わり税負担が増える
前述したように、木造や一部の鉄骨造のアパートの場合、築30年を過ぎると法定耐用年数を超えてしまいます。
法定耐用年数を超えた建物は、減価償却ができません。
たとえば、耐用年数が20年の木造アパートを2500万円で購入した場合、購入費用を20年間で割った125万円を減価償却費として計上することで、所得税や法人税を減税できます。
しかし、築30年になるとすでに減価償却期間が終了しているため、購入費用を減価償却費として計上できません。
毎年の税負担や、定期的な修繕費用の負担に困っている方は、アパートの売却について不動産会社に相談してみましょう。
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





