不動産投資の拡大戦略が必要なタイミングは?やってはいけない注意点も紹介
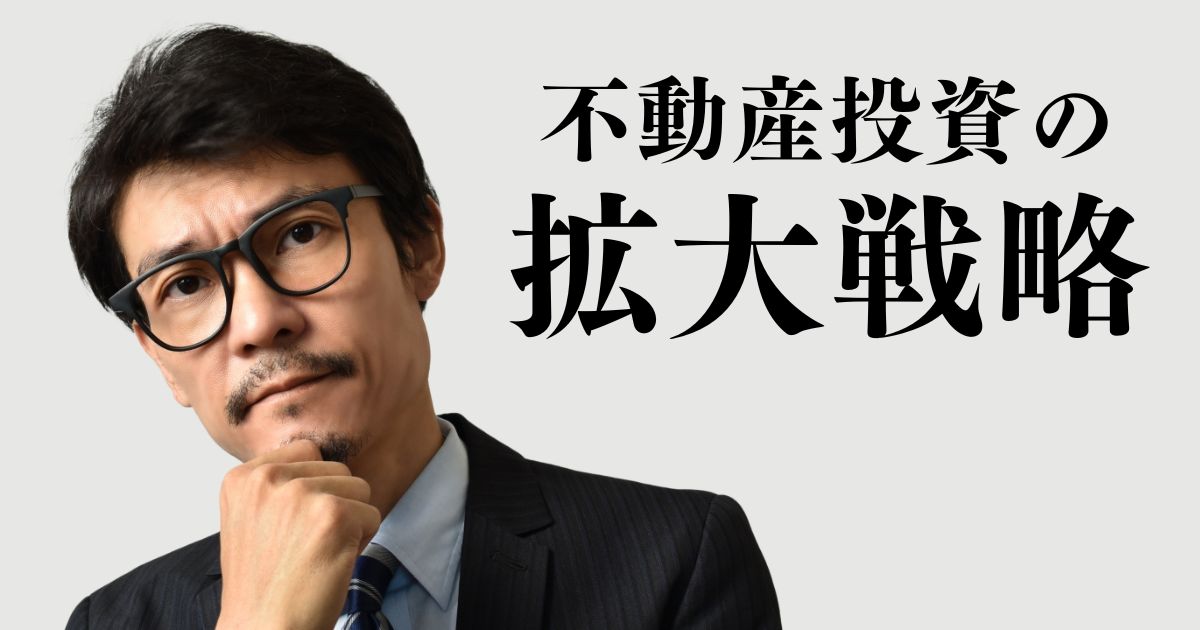
投資物件の購入から時間が経ち、買い増しを検討している方もいるでしょう。2棟目以降の購入には、家賃収入の増加や投資リスクの分散など、さまざまなメリットがあります。
しかし買い増しを行うタイミングを見誤ると、思わぬ失敗をしてしまうかもしれません。この記事では、不動産投資の拡大戦略を実行すべきタイミングや、やってはいけない注意点について解説します。
この記事の目次
不動産投資の拡大戦略を実行すべき4つのタイミングとは?
不動産投資の拡大戦略を実行すべきタイミングは4つあります。
- 1棟目の決算書が黒字化したとき
- 1棟目の空室率が低く、ほぼ満室の状態が続いているとき
- 資金的な余裕ができたとき
- 建物の減価償却期間が終わったとき
ポイントとなるのは、1棟目の投資物件の経営状況です。また資金的な余裕や、建物の減価償却期間なども考慮し、拡大戦略を実施するタイミングを見極めましょう。
1棟目の決算書が黒字化したとき
不動産投資の拡大戦略を実行すべきタイミングのひとつは、投資物件の経営が軌道に乗り、決算書が黒字化したタイミングです。
投資物件の買い増しにあたって、金融機関から追加の融資を受けようと考えている方もいるでしょう。融資審査に通るためには、原則として1棟目の決算書が黒字である必要があります。
また投資物件をきちんと収益化できており、十分な担保評価が得られる場合は、1棟目を担保として不動産投資ローンを借りることも可能です。そのため1棟目の決算書が黒字化した段階で、投資物件の買い増しを検討するとよいでしょう。
1棟目の空室率が低く、ほぼ満室の状態が続いているとき
また投資物件の空室率が低く、年間を通じてほぼ満室の状態を維持できているケースも、拡大戦略を実行すべきです。
空室率は、金融機関の融資審査において重要な指標のひとつです。空室率が高い不動産は、十分な家賃収入が見込めないため、金融機関にとって貸し倒れリスクが高くなります。
全国賃貸住宅経営者協会連合会の「民間賃貸住宅(共同住宅)戸数及び空き戸数並びに空き室率の推計」によると、平成30年度における全国の賃貸物件の空室率(空き室率)は21.4%です。空室率が全国平均を下回ったからといって、必ずしも融資を受けやすくなるわけではありませんが、ひとつの目安としてください。
資金的な余裕ができたとき
手元の資金にある程度の余裕ができたタイミングも、拡大戦略の実行におすすめです。
不動産投資の健全性を測る際は、フリーキャッシュフローという指標が使われます。フリーキャッシュフローとは、文字通り企業や個人が自由に使えるお金を意味し、以下の計算式で求めることが可能です。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー - 投資キャッシュフロー
営業キャッシュフローは事業活動から生まれたキャッシュフローのことで、不動産投資では主に家賃収入から経費やローンの支払いを差し引いたものを指します。また投資キャッシュフローは事業維持のためのキャッシュフローのことで、不動産投資では主に大規模修繕や設備投資、将来の買い増しのための積立金を指す単語です。
アパートやマンションなどの投資物件は、定期的に大規模修繕を実施する必要があります。大規模修繕に向けた積み立てを行ってもなお、フリーキャッシュフローが黒字である場合は、2棟目の購入を検討するとよいでしょう。キャッシュフローに余裕があれば、物件購入時の頭金も確保できます。
建物の減価償却期間が終わったとき
建物の減価償却期間が終わったタイミングも、拡大戦略を実行すべきタイミングのひとつです。
アパートやマンションなどの建物は、法定耐用年数に基づいて減価償却期間が決められています。減価償却期間が終わると、投資物件の取得費用を耐用年数で割り、分割して経費計上する節税対策を行えなくなります。
主な建物の減価償却期間は以下の通りです。
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 木造・合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 24年 |
| 店舗用・住宅用のもの | 22年 | |
| 木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 22年 |
| 店舗用・住宅用のもの | 20年 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 50年 |
| 住宅用のもの | 47年 |
※参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
木造アパートの場合は、築年数が22年経つと減価償却期間が終わります。減価償却が終わる時期が近づいている場合は、それ以上の節税ができなくなるため、買い増しを検討するとよいでしょう。
不動産投資の拡大戦略には2種類ある
不動産投資の拡大戦略は、大きく2種類に分けられます。
- 新たな投資物件を買い増しする
- より資産価値の高い投資物件に買い替える
それぞれの方法を解説します。
新たな投資物件を買い増しする
不動産投資の拡大戦略のひとつは、新たな投資物件を買い増しする方法です。
不動産経営は分散投資の観点から、投資物件を複数所有することが望ましいといわれています。2棟目や3棟目には、1棟目で培った経験やノウハウを生かせるため、経営状況を安定させやすいのがメリットです。また収益性が高い物件を買い増せば、大幅な収入アップにつながるでしょう。
ただし1棟目のローンが残った状態で買い急ぐと、毎月の返済負担が増加し、財務状況の悪化につながるリスクもあります。
より資産価値の高い投資物件に買い替える
もうひとつの拡大戦略は、投資物件から得られる利益を活用し、より資産価値の高い不動産に買い替える方法です。たとえば投資物件の売却益(キャピタルゲイン)や、長期運用による家賃収入などにより、資産規模の拡大を目指します。
地価の上昇などを利用し、短期間で大きなキャピタルゲインを狙う手法は現実的ではないため、基本的には中長期的な視点で資産を育てていきます。投資物件を売却するタイミングによっては、売却損が生じるリスクがあるため、不安な方は不動産運用の専門家に相談しましょう。
不動産投資の拡大戦略でやってはいけない注意点3つ
ここでは、不動産投資の拡大戦略において避けるべき注意点を3つ紹介します。
- 1棟目と同じ地域・エリアの不動産を選ばない
- 1棟目と築年数が近い不動産を選ばない
- 管理会社はできるだけ分散させない
それぞれについて注意すべき理由を解説します。
1棟目と同じ地域・エリアの不動産を選ばない
投資物件を買い増すときは、同じ地域・エリアの不動産を選ばないようにしましょう。同じ地域・エリアの物件を複数所有すると、以下のようなリスクが生じるからです。
- 火災や自然災害が起きたときに投資物件が同時に被災し、多額の負債を負う可能性がある
- 賃貸需要が似ているため、空室率の増加や家賃の値下げなどのリスクをヘッジできない
1棟目とは異なる地域・エリアの物件を購入することで、投資リスクを分散させ、収益の安定性を高められます。
1棟目と築年数が近い不動産を選ばない
1棟目と築年数が近い不動産を選ばないことも大切です。築年数が近いと、建物の大規模修繕のタイミングが重なり、短期間で多額の出費が発生するからです。築年数にばらつきのある物件を保有することで、大規模修繕の時期を分散し、キャッシュフローが悪化するリスクを抑えられます。
また築年数が古い物件を所有している場合は、より築年数が新しく、資産価値が高い物件を買い増すとよいでしょう。1棟目の担保評価を底上げでき、将来3棟目を購入する際に融資が受けやすくなるからです。
不動産管理会社はできるだけ分散させない
2棟目や3棟目以降の管理業務は、可能であれば1棟目の不動産管理会社に委託し、一元管理してもらうとよいでしょう。他の管理会社を探したり、個別にやりとりしたりする手間がかかりません。
すでに担当者の人柄や仕事ぶりが分かっているため、信頼して管理を任せられるという利点もあります。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
鳥塚 正人
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





