不動産投資で2棟目の融資は受けられる?融資審査に通るポイントを解説
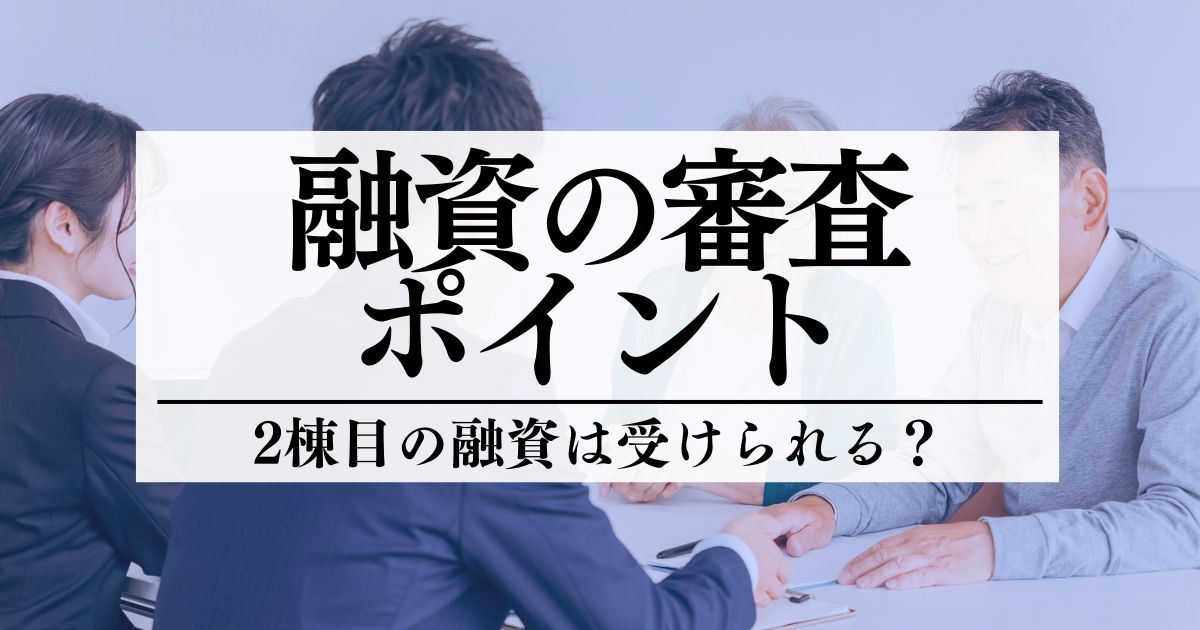
不動産投資が軌道に乗り、2棟目の購入を検討している方もいるでしょう。
そこで問題となるのが、不動産投資ローンの融資審査を通過できるかどうかという点です。一般的に2棟目以降の購入物件の融資審査は、1棟目よりもハードルが高くなるといわれています。
この記事では、不動産投資において2棟目の融資審査に通るポイントや、ローンに落ちたときの対処法について解説します。融資を追加で受けられるよう、解説するポイントを参考に、2棟目の不動産投資を検討してみてください。
この記事の目次
不動産投資のローンが残っていても2棟目の融資は受けられる?
1棟目の不動産投資ローンがまだ残っていても、2棟目の融資を受けることは可能です。特に1棟目の不動産を収益化できており、経営状況が安定していることを融資担当者にきちんと説明できる方なら、追加の融資を受けられる可能性は高くなるでしょう。
ただし個人の属性や1棟目の経営状況、金融機関ごとの融資条件によっては、融資が難しいケースもあります。たとえば、以下のような場合です。
- 年収や職業(勤務先)、保有する金融資産などの属性面が弱い
- 1棟目を購入してから、ほとんど時間が経っていない
- 不動産投資の経験が1棟目の物件しかない
- 1棟目の物件の決算書に不安要素がある
- そもそも融資対象物件が1棟目の購入物件のみ
2棟目の融資を受けるには、金融機関の担当者に「この人なら、追加の貸付をしても大丈夫」と感じてもらえるような判断材料を用意する必要があります。
そのため1棟目にどのような物件を選ぶかによっても、2棟目の融資審査の難易度は変わります。空室リスクの対策がしやすく、キャッシュフローが黒字化しやすい物件なら、2棟目も不動産投資ローンを借りやすくなるでしょう。将来的な2棟目の購入も見据え、計画的に不動産経営を行うことが大切です。
2棟目を購入するときの融資審査の3つのポイント
2棟目の融資を受けやすくするには、1棟目購入後の対応が重要になってきます。融資審査に通るためのポイントは3つあります。
- 1棟目の決算書は毎年提出する
- 決算書は黒字を維持する
- 1棟目をローンの担保にする
それぞれのポイントについて解説します。
1棟目の決算書は毎年提出する
金融機関に融資の申し込みをする際に、必要とされる書類には以下のようなものがあります。
- 決算書(個人の方は確定申告書)
- 納税証明書
- 試算表
- 商業登記簿謄本
- 資金繰り表
- 事業計画書など
融資審査において、特に重要とされるのが決算書(確定申告書)です。2棟目も融資を受けたい方は、決算書を毎年提出するようにしましょう。金融機関からの要望がなくても、こちらから決算書を送ることをおすすめします。
すでに不動産を購入している方の場合、融資担当者は主に決算書の内容から、1棟目の収益性や経営状況を判断します。決算書や確定申告書を提出しない場合、担当者は物件の状況を確認できないため、融資がおりる可能性はほとんどありません。
決算書を毎年提出すれば、担当者が小まめに経営状況を確認できます。経営状況が安定していれば、2棟目や3棟目も融資を受けられる確率が高まるでしょう。
決算書は黒字を維持する
2棟目の融資を受けるなら、1棟目の決算書が黒字かどうかも重要です。赤字決算が続いている場合、事業計画やビジネスモデルに十分な説得力がないかぎり、追加融資を受けられる可能性は低くなります。
不動産投資ローンの審査において、決算書で見られるポイントには以下のようなものがあります。
- 黒字決算か
- キャッシュフローが健全か
- 自己資本比率が高いか
- 債務償還可能年数が長過ぎないか
自己資本比率とは、総資本のうち純資産(新株予約権を除く)の占める割合のことです。
また、債務償還可能年数とは、業務活動の黒字分を償還財源に充てた場合に何年で債務を償還できるかを示す理論値のことです。
融資担当者はこうした指標を通じて、借り手に返済能力(支払い能力)があるか、1棟目の事業に継続性があるか、の2点を判断しています。なかなか融資を受けられず苦労している方は、決算書の黒字化はもちろん、自己資本比率や債務償還可能年数といった指標の改善にも取り組みましょう。
1棟目をローンの担保にする
2棟目の融資を受けるため、1棟目を不動産投資ローンの担保にするという方法もあります。
ただしこの方法は、1棟目の土地や建物に十分な担保評価がある場合に限られます。担保にした不動産は、返済不能に陥ったときに売却され、貸し倒れを防ぐ役割があるからです。
たとえば1棟目の不動産が赤字経営だったり、空室が多くほとんど利益が発生していなかったりする場合、ローンの担保にすることは原則できません。
その点でも1棟目の物件選びが、2棟目や3棟目以降の融資の受けやすさに影響してきます。
2棟目の不動産投資でローンに落ちたときの対処法2つ
もし2棟目の不動産投資ローンの審査に落ちてしまったら、2つの方法で対処しましょう。
- 1棟目の経営状況を改善する
- 念のため信用情報を確認しておく
1棟目の経営状況を改善する
2棟目の融資を受けるには、原則として1棟目の決算書(確定申告書)が黒字である必要があります。1棟目の不動産の経営状況を改善することで、融資審査に通る確率を高められます。
1棟目の経営がうまくいっていない場合は、以下のような対策を実施しましょう。
- 空室率を改善し、満室に近い状態を維持する
- 経費の削減を行い、キャッシュフローを黒字化する
それぞれの対策方法について具体的に解説します。
空室率を改善し、満室に近い状態を維持する
空室率とは、アパートやマンションなどの物件の部屋数全体のうち、空室になっている部屋数の割合のことです。空室率は不動産の収益性に大きく影響する指標のひとつで、以下の計算式で求められます。
空室率=(空室数×空室期間)÷(全体の部屋数×365日)×100
安定した入居者を確保し、満室に近い状態を維持することで、家賃収入が増え経営状況の改善につながります。空室率を改善する施策として、たとえば以下のようなものがあります。
- 建物が老朽化している場合はリフォームを計画する
- セキュリティの強化や、入居者に人気の設備を導入する
- 長期入居に対するインセンティブ(家具や家電のプレゼントなど)を用意する
- 国土交通省の住宅セーフティーネット制度を利用し、高齢者や低所得者、障害者などの受け入れを検討する
経費の削減を行い、キャッシュフローを黒字化する
1棟目のキャッシュフローの健全化に取り組むことも大切です。何から手を付ければよいか分からない場合は、経費率に目を向けるとよいでしょう。
経費率とは、収入(家賃収入)に対する必要経費の割合を表す指標で、以下の計算式で求められます。
経費率=必要経費÷家賃収入×100
不動産経営における主な経費には、以下のようなものがあります。
- 管理費・管理委託手数料
- 修繕費・原状回復費用
- 入居者募集費用
- 仲介手数料
- 損害保険料(火災保険料や地震保険料など)
- ローンの利息部分
こうした経費の見直しを行い、削減できるものがないか確認してみましょう。たとえば金利が低いローンへの借り換えや、損害保険会社の変更、共用部分の光熱費の節約、管理業務を委託する不動産管理会社の見直しなどが考えられます。
念のため信用情報を確認しておく
融資審査に落ちる理由に心当たりがない場合は、念のため信用情報を確認しておくとよいでしょう。個人の信用情報を収集し、管理している機関は3つあります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 一般社団法人 全国銀行協会(全銀協)
- 指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構(JICC)
インターネットでの開示請求もできるため、過去にローンやクレジットカードの支払いの延滞がないか、金融事故情報が登録されていないか、といった点を確認してみましょう。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
飯野一久
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





