アパートの相続税評価額を解説|相続後は運用?それとも売却?
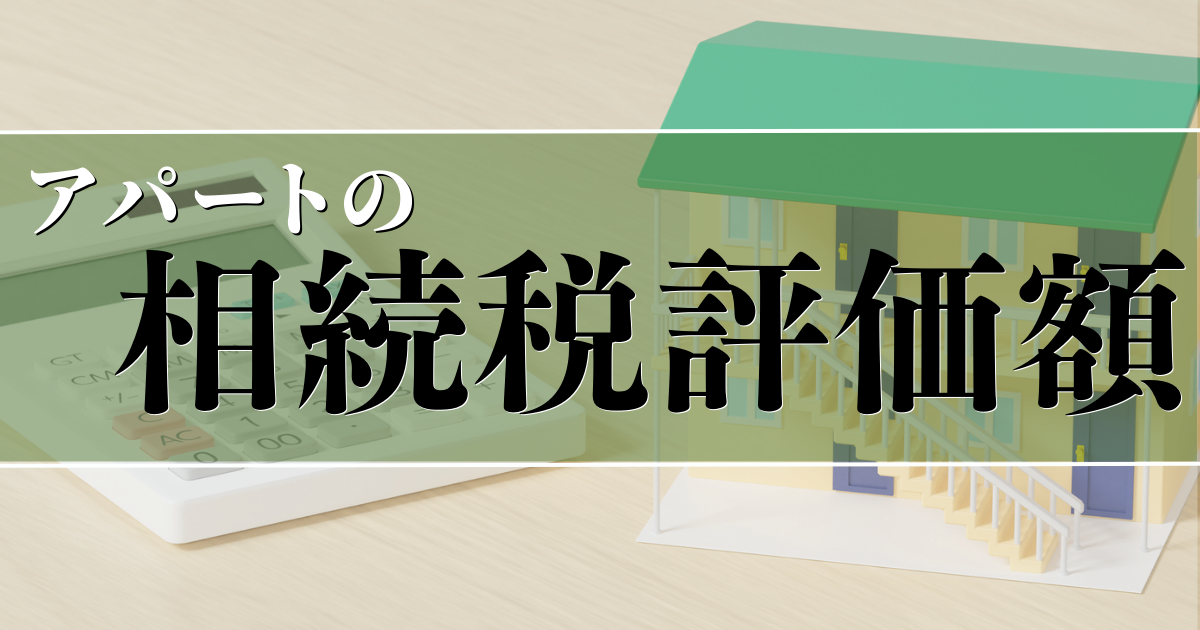
アパートは相続税対策として有効であるといわれますが、実際にアパートの相続税評価額はどのくらいなのでしょうか。
アパートの相続税評価額の計算を具体例を用いながら解説します。また、相続後の運用・売却についても紹介します。
この記事の目次
アパートの相続税評価額
不動産の相続税を計算する場合、土地と建物で評価額の求め方が異なります。つまり、アパートを相続した場合、土地と建物を別々に評価する必要があります。
建物の相続税評価額
建物の評価額は、固定資産税評価額と同額です。固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書で確認できます。
自治体によって異なりますが、納税通知書は毎年4月〜6月に届くことが一般的です。
路線価を用いてた土地の相続税評価額
土地の相続税評価額は建物と異なり、以下の2種類により計算します。
- 路線価を用いる計算方法(路線価の設定がある土地)
- 評価倍率を用いる計算方法(路線価の設定がない土地)
路線価を用いる計算方法
路線価の設定がある地域の土地の相続税評価額は、以下のように求めます。
路線価とは、国税庁が定める路線(道路)ごとの1㎡あたりの金額であり、千円単位で記載されています。国税庁の「財産評価基準書」から確認ができます。
路線価は年1回発表され、価格変動によって納税者間で不公平が生じないよう、時価の8割程度を目安に定められています。
地積とは、土地の面積のことであり、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。納税通知書がない場合は、土地の登記簿謄本でも確認できます。
補正率とは、宅地の形状に応じて土地の価値を把握するための割合をいいます。路線価は土地の個別事情までは考慮していないため、相続する土地の形状等を把握し、国税庁が公表している補正率を調べる必要があります。
国税庁が公表している主な補正率は下記のとおりです。対象の土地形状をしっかり把握し、間口と奥行きの状態や土地の道路接道により、どの補正率を使用できるか確認していきます
| 補正率 | 特徴 |
|---|---|
| 奥行価格補正率 | 平均的な奥行と比べて、短い、あるいは長い |
| 側方路線影響加算率 | 正面と側面に道路がある土地(角地) |
| 二方路線影響加算率 | 正面と裏面に道路がある土地 |
| 間口狭小補正率 | 道路に接する間口が狭い土地 |
| 不整形地補正率 | 正方形や長方形ではなく、いびつな形状の土地 |
たとえば、下記条件のアパートの土地Xの相続税評価額は、以下のように計算します。
- 条件:路線価100千円/㎡ 地積200㎡ 補正率0.8
- 土地Xの相続税評価額=路線価100(千円/㎡)×地積200(㎡)×補正率0.8=16,000万円
評価倍率方式を用いた土地の相続税評価額
路線価の設定がない地域の土地の相続税評価額は、以下のように求めます。
すべての道路に路線価が設定されているわけではありません。市街化調整区域と呼ばれ、都市計画で市街化を抑制すべき地域として定められるエリアなどは、路線価が付されていないことが一般的です。
このように路線価がない地域では、評価倍率を用い自分で相続税評価額を計算します。
たとえば、下記条件のアパートの土地Yの相続税評価額は、以下のように計算します。
小規模宅地等の特例の対象となる土地の相続税評価額
相続したアパートで一定の要件を満たす場合、小規模宅地の特例を適用できます。
小規模宅地等の特例は、賃貸アパートやマンションなど不動産貸付業に使われていた土地以外に、相続開始時点で被相続人と同居したり、事業を一緒に運営したりしていた場合や住宅として使われていた土地で適用できます。
| 土地の種類 | 限度面積 | 減額される割合 |
|---|---|---|
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
たとえば、下記条件のアパートの土地Zの相続税評価額は、以下のように計算します。
- 条件:土地Zの相続税評価額1,000万円 賃貸アパートとして利用していた土地200㎡
- 土地Zの相続税評価=1,000-(1,000×50%)=500万円
アパートを含めた相続税の計算
相続税評価額は不動産のみ計算するのではなく、相続財産すべてで計算する必要があります。詳しくみていきましょう。
相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算
相続財産とは、被相続人が死亡時点で所有していた権利や義務であり、アパートなどの不動産のほか、被相続人の預貯金、現金、証券、車、貴金属などがあります。
相続税を計算するには、まず相続税の課税対象となる課税遺産総額を求めます。計算方法は以下のとおりです。
- 相続財産の評額(遺産総額)と相続時精算課税の適用を受ける財産の評価を合計
- 1から債務、葬式費用、非課税財産を差し引く→「遺産額」
- 遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価格を加算→「正味の遺産額」
- 3から基礎控除額※1を差し引く→課税遺産総額
※1 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の計算
課税遺産総額が求められたら、以下の手順で相続税を計算します。
- 課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それぞれ税率を適用して、各法定相続人別に税額を計算
- 1の税額の合計が相続税の総額
- 2の相続税の総額を実際の相続割合で按分
- 3から配偶者の税額軽減、各種の税控除を差し引いて、実際に納める税額を計算
たとえば、以下のケースで計算してみます。
- 遺産額:アパートの土地および建物の評価額1億円 現預金1億円 証券5千万円
- 相続人:妻A、子B、子C
- 1.課税資産総額を法定相続分で按分
- 妻Aの相続財産:20,200万円×1/2=10,100万円
- 子Bの相続財産:20,200万円×1/4=5,050万円
- 子Cの相続財産:20,200万円×1/4=5,050万円
国税庁の「相続税の速算表」から、
- 10,100万円の場合、税率40%で控除額1,700万円
- →妻Aの相続税:2,340万円
- 5,050万円の場合、税率30%で控除額700万円
- →子Bの相続税:815万円
- →子Cの相続税:815万円
- 2.相続税の総額
- 2,340万円+815万円+815万円=3,970円
- 3.相続税の総額を実際の相続割合で按分
- 妻Aの相続割合:3,970万円×1/2=1,985万円
- 子Bの相続割合:3,970万円×1/4=992.5万円
- 子Cの相続割合:3,970万円×1/4=992.5万円
- 4.実際に納める税金
- 妻Aの相続税:0円※2
- 子Bの相続税:992.5万円
- 子Cの相続税:992.5万円
※2 配偶者の税額軽減により、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までは、配偶者に相続税はかからない
相続したアパートは運用?それとも売却?
アパートを相続した場合、運用を継続するまたは売却する方法があります。
アパートを運用するメリットやデメリット
アパートを運用する最大のメリットは毎月の家賃収入を得ることです。これにより、収入の安定性が生まれます。
また、賃貸収入の増加や地価の上昇などによって、相続したアパートの価値が上がる可能性があります。そして、不動産は経済変動に強くインフレ対策になるといわれてます。
一方で、アパートの運用には賃借人対応や修繕などの手間がかかるデメリットがあります。その他、不動産の価格下落リスクや、空室や賃料滞納リスク、自然災害リスクなど不動産投資に関するリスクを負うデメリットがあります。
また老朽化による修繕費用や管理費用が増加する可能性があります。
アパート売却はコストがかかる
アパートを運用しても期待通りの収益が見込めない場合や不動産投資に関するリスクを抱えたくない場合、アパートを売却する選択が生まれます。
アパートを売却する場合、売却に関するコストや税金を把握しておく必要があります。主なコストは以下のとおりです。
- 仲介手数料
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登録免許税
なお、譲渡所得税はアパートの保有期間によって税率が異なります。売却した年の1月1日までの期間が5年超の場合、長期譲渡所得といい税率20.315%、5年以下を短期譲渡所得といい税率は39.63%です。
相続したアパートを運用または売却する場合、いずれも不動産取引に関する相応の経験や知識が必要です。間違った判断などを行わないため、親身になって相談できるプロの不動産会社に相談することをおすすめします。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
飯野一久
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





