立ち退きの相談はどこにする?立ち退き料の相場や抑え方も解説
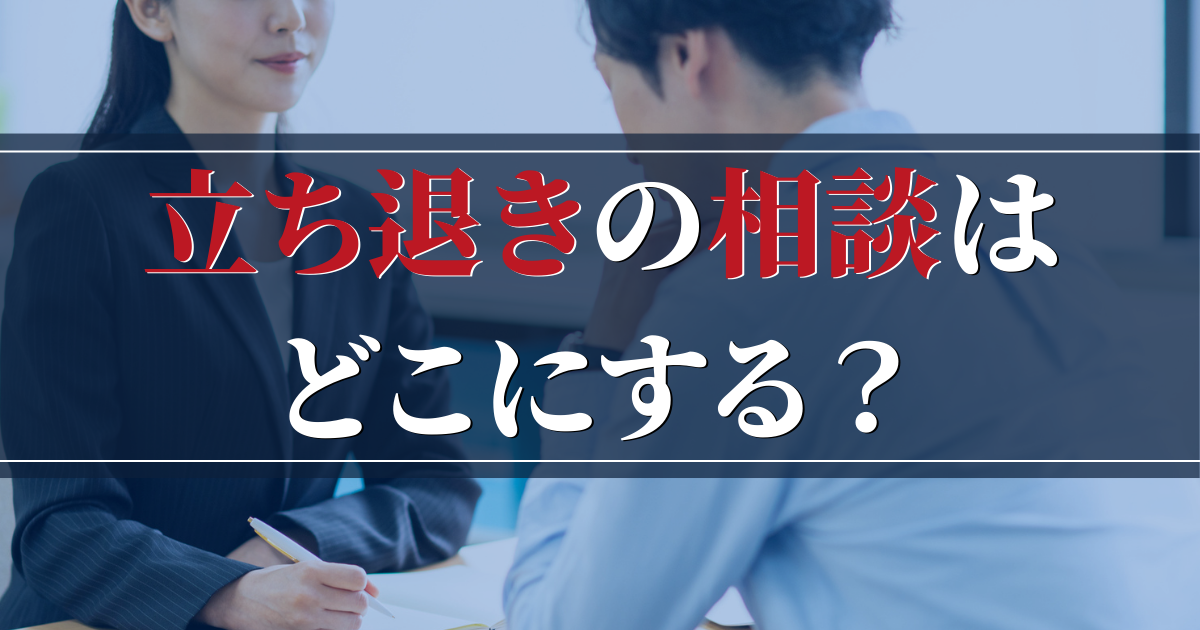
貸し出しをしている物件に「親族を住まわせたい」、「建て替えたい」などを理由に現入居者に立ち退いてもらいたいと思うことがあります。
立ち退きは当事者間だけで容易に解決できるものではありません。ではどこに相談すればよいのでしょうか。相談先や費用相場などについて解説します。
この記事の目次
立ち退きの相談はどこにする?
立ち退きの相談は賃貸人と賃借人が直接行っても構いません。しかし、賃借人が立ち退きに応じないなど、トラブルが起きるおそれがある場合は第三者に相談したほうがスムーズです。
立ち退きの相談先としては、弁護士、各種協会、地方自治体などが挙げられます。それぞれの相談先の特徴と、相談する際の注意点について解説します。
弁護士
弁護士に立ち退き交渉の代行依頼をすることで、スムーズに立ち退きを進められます。
立ち退き交渉には専門知識と交渉力が必要です。立ち退き交渉に強い弁護士であれば、正当な事由を元に適切な立ち退き料を設定できます。また、専門知識に基づいた冷静な交渉ができるため、賃借人の納得を得られやすい点もメリットです。
ただし、弁護士に依頼するとそれだけ費用がかさみます。依頼する事務所によって異なりますが、相談料が1時間当たり5,000円~1万円、交渉を依頼すると30~40万円程度費用がかかると考えておくとよいでしょう。
費用を抑えたい場合は法テラス(日本司法支援センター)の利用も検討しましょう。法テラスとは国が設立した法律トラブルの相談所で、弁護士による30分程度の無料相談を受けられます。収入や資産が一定の基準以内であれば利用可能です。
各種協会
賃貸経営に関するトラブル解消をサポートする協会に相談するのもひとつの選択肢です。
弁護士のように交渉代行は依頼できませんが、一般的な見解や基本的な情報を教えてもらうことは可能です。主な相談先としては以下のような団体が挙げられます。
賃貸住宅経営者の支援を行っている団体です。賃貸経営に役立つセミナーや講演会も開催しています。
賃貸住宅の賃貸人・賃借人への相談を行っている団体です。「安心ちんたいコールセンター」を開設しており、無料で相談できます。ただし、法律の専門家はいないため、受けられるのは一般的なアドバイスに限られます。
住宅産業に起因する紛争の相談を行っている団体です。ADR(裁判外紛争解決手続き)により、和解・調停・仲裁による紛争解決をサポートします。裁判を介さないため費用が安く、非公開のうちにトラブル解決に結びつく可能性があります。
法務・税務・不動産などの専門知識を有する80名以上の顧問団が、立ち退きや家賃滞納、契約違反、リフォーム工事のトラブルなど、不動産トラブルに関する相談を受け付けます。
地方自治体
地方自治体の相談窓口に相談することも可能です。
地方自治体の中には、紛争解決への助言やあっせん、紛争解決制度などの情報提供を行ったり、民間団体と協力して立ち退きトラブルに関する相談窓口を設けたりしている場合もあります。
サポート内容は地方自治体によって異なります。お住まいの市区町村・都道府県に確認してみるとよいでしょう。
立ち退き料の相場、不要なケースもある?
立ち退き料の相場や立ち退き料を支払うべきケース、支払わなくてもよいケースについて解説します。不要な支払いをすることがないよう、立ち退き料の基礎知識を押さえておきましょう。
立ち退き料の相場とは
立ち退き料には明確な規定がありません。あくまで賃貸人・賃借人の合意の下で決められるものであり、金額の設定もまちまちです。
裁判によって立ち退き料が定められる際も、個々の事案ごとに異なる算定方法が用いられています。
一般的には賃料の6〜12カ月分ともいわれていますが、地域や状況によって立ち退き料は大きく変わります。相場にこだわるのではなく、賃借人が納得できるような金額や条件を提示し、誠実な対応をすることが重要です。
立ち退き料が必要なケース
原則として、貸主都合による立ち退きの場合は立ち退き料が必要です。貸主都合と見なされるケースとしては、以下のようなものがあります。
- 所有者や他の人が住むことになった
- 物件の大規模修繕や建て替え
- 再開発により物件の建っている土地を売却する
立ち退き料が不要なケース
立ち退き料は必ずしも必要なものではありません。賃借人が立ち退きに応じている場合や、契約違反に該当しない場合は立ち退き料を支払う必要はありません。
賃借人が立ち退きに応じている
貸主都合の立ち退きであっても、賃借人が立ち退きに応じている場合は立ち退き料を支払わなくても構いません。
普段から信頼関係を築いておき、早い段階で誠実に立ち退きをお願いすることで、立ち退きに快く応じてもらえる可能性があります。
契約期間が契約で定められている
契約期間が契約で定められている場合、契約満了後であれば退去を求めても問題はなく、立ち退き料も必要ありません。該当する契約としては、以下のようなものがあります。
- 定期建物賃貸借契約:更新がないことをあらかじめ定めた契約
- 一時利用目的の賃貸借契約
ただし、契約書への記載や契約者への説明が不十分であると見なされた場合は、立ち退き料が発生する場合があります。
賃借人に契約違反があり、賃貸借契約を解除できる
賃借人が明らかに契約違反をしている場合も立ち退き料は不要です。
たとえば家賃を滞納している、ペット禁止の物件でペットを飼っている、無許可で転貸しているといったケースが該当します。このような重大な契約違反を賃借人が行った場合、賃貸人は退去通知をすることができるため、立ち退き料は必要ありません。
ただし、退去通知をするためには、信頼関係を大きく損なうとされる正当な事由と、6カ月前の予告が必要とされます。契約違反をしたから即日立ち退きをしてもらえるわけではありません。
立ち退き料を抑える方法は?
立ち退き料には規定がありません。賃借人ともめてしまった場合は高額の立ち退き料を求められるおそれもあります。とくにアパート一棟すべての住人に立ち退き料を支払うとなると、払いきれないほどの莫大な金額になってしまうおそれもあります。
立ち退き料を抑えるためには、どのような点に気をつければよいのでしょうか。具体的な方法を紹介します。
賃借人との信頼関係を築いておく
賃借人の同意があれば、立ち退き料の支払いは必要ありません。
普段から賃借人の要望や不満点に誠実に応え、信頼関係を築いておくことで、立ち退きやその他の交渉に快く応じてもらえる可能性が高まります。
入居者を減らしてから交渉を始める
立ち退きまでに時間的余裕がある場合は、自然退去による入居者の減少を待ちましょう。
たとえば、数年後に取り壊しが決まっているのであれば、退去時に新たに入居者を募集しない、もしくは定期借家契約で契約するとよいでしょう。
立ち退きの交渉相手を減らすことで、立ち退き料や交渉の手間を軽減できます。
退去時の負担を減らす
退去時の負担を減らすことで、立ち退き料の減額交渉が有利に運ぶ可能性があります。具体的な方法を紹介します。
引っ越し先の提供
現在の住居を退去するとなると、お金の面だけではなく、新しい住居を探すことも賃借人の大きな負担になります。
類似物件を所有している場合は、引っ越し先として提供することで退去時の負担を減らせます。引っ越し先の賃貸借契約時に敷金の減額やフリーレント期間の設定を約束することも、強力な交渉材料になるでしょう。
退去までの賃料を減額する
退去までの賃料を減額したり、フリーレント期間を設けたりすることを条件に、立ち退き料の減額交渉をするのもひとつの方法です。
もちろん家賃収入は減りますが、立ち退き交渉が泥沼化したときの手間や費用を考えれば、賃貸人にとってもメリットは少なからずあるでしょう。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
鈴木 和典
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





