築30年のアパートは資産価値がない?経営を続けるデメリットや手放す方法
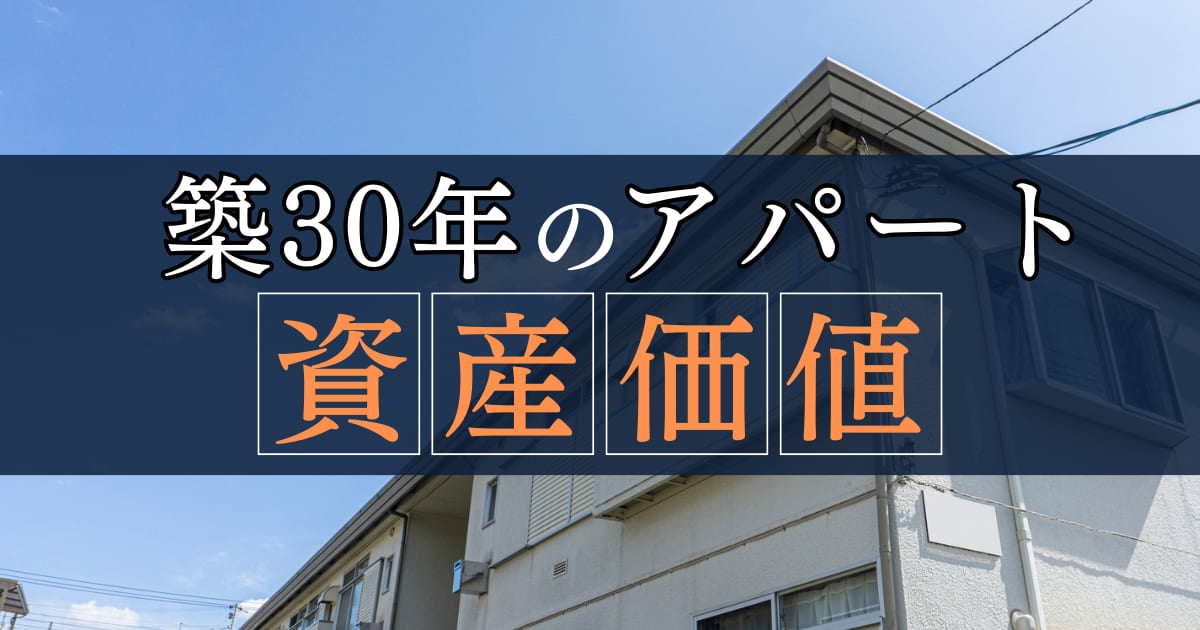
建物は、どれだけメンテナンスなどを丁寧に行っていても、築年数の経過に伴う老朽化によって資産価値は少しずつ確実に低下していきます。
築30年のアパートの場合、修繕費や税金の負担が多く、収益率が低いため、今後も賃貸経営を続けるのは困難といえるでしょう。
この記事の目次
築30年のアパートは資産価値がない?
まずはアパートの資産価値について考えてみましょう。
アパートの価値を決める要素
アパートの価値を決める要素はいくつかありますが、ひとつは立地です。
- 交通機関からの距離が近い
- 教育施設が充実している
- 買い物が便利
人によって重視するポイントはそれぞれ異なりますが、特に駅近の不動産は人気が高いため、資産価値を保ちやすい傾向にあります。
また、広さや築年数も資産価値を左右する要素です。
これらの要素を大きく分けると、変わることのない「不変的な項目」と、年数や状況により変動する「変動的な項目」があります。
| 不変的な項目 | 変動的な項目 |
|---|---|
| 立地 | 築年数 |
| 広さ・間取り・階数 | 賃料 |
耐用年数と寿命
法定耐用年数は、国税庁が税金算出の観点から、アパートなどの資産について「使用できるであろう期間」を定めたものです。
しかし、法定耐用年数を超えたからといって、使えなくなるわけではありません。法定耐用年数が経過したあとも居住することが可能です。もちろん売買取引を行ったとしても法律違反とはなりません。
一般的なアパートである木造2階建ての場合、法定耐用年数は22年であり、築30年の場合のアパートはすでに経過していることになります。
一方で、法定耐用年数が22年なのに対して、実際に使用できる年数を示した物理的耐用年数は約65年とされており、その差が43年と大きく開いてる点は注目です。
法定年数はあくまで減価償却費などの税制面で使用される年数であり、建物の寿命よりも短く設定されているといえます。
メンテナンス状況による価値低下の違い
アパートは空室が続いていると、換気などがされないことから傷みが早くなっていきます。
空室の解消にはメンテナンスが重要であり、ここを怠ると入居者の満足度が下がり、退去率が増加します。そして、以下のような”負のループ”に突入します。
- 新しい入居者を探しにくくなるため、空室が長期化する
- 家賃収入が減り、建物が傷んでいく
- 収入がないのでメンテナンスができない
- 退去が増え、建物が傷んでいく
しっかりとした計画のもとで予防修繕や大規模修繕を行い、建物の管理をすることは、建物を長期的に使用するだけではなく、資産価値を保つためにも重要です。
築30年のアパートで賃貸経営を続けるデメリット
築年数が経過したアパートは老朽化が始まり、メンテナンスが必要になります。
アパートの一番収益率が高い時期は、間違いなく建設直後の新築物件のときでしょう。年数の経過で家賃を下げることはあっても上がることはなく、それに対してメンテナンス費用などの支出が増加します。
築30年を経過したアパートで賃貸経営を行うことに対するメリットは少なく、デメリットが多いといえるでしょう。
修繕費用がかさむ
アパートでは、築年数が経過するほど修繕費用は増加します。
- 屋上防水や壁の亀裂などの浸水に対する予防や修復
- 古くなった給湯器や水回りなどの設備交換
上記のような対応が必要になる場面が増えていきます。
築30年のアパートで賃貸経営を行うことは、メンテナンス費用との戦いでもあります。
税負担の増加
法定耐用年数の期間内であれば、建物の価値低下を減価償却費として加味し、税金を減額できます。
減価償却費を求める方法はいくつかありますが、以下の計算式で求められます。
減価償却費=取得費用 × 償却率
建築費用が2億円の木造アパートであれば、償却率は法定耐用年数22年の0.46が適用されるため、計算式は以下のとおりです。
減価償却費=2億円 × 0.046=920万円
毎年、920万円の減価償却費を経費から差し引けるため、税額を抑えられます。
しかし、これはあくまで法定耐用年数の間が対象です。築30年のアパートであれば22年を経過しており減価償却期間を終えているため、減税の対象外です。
アパート経営において減価償却による節税が可能なのかは、損益分岐点に対しても大きな意味合いがあります。
収益率の低下
たとえば、最寄駅まで徒歩5分、広さは26平米のワンルームで家賃も8万円の2つの物件があるとしましょう。片方は新築物件で片方は築30年経過した物件であれば、どちらを選ぶかと聞かれたら、よほどの事情がない限りは新築物件を選ぶ方が圧倒的多数でしょう。
また、アパートの経営を検討する土地所有者や不動産投資家は多く、次々と新しい物件が増加する傾向にあります。
その中で築30年のアパートが入居率を高くするには、「家賃を下げる」ことが簡単であり、最も効果的な施策と考えられます。しかし、メンテナンス費用という支出が増えているなかで家賃収入を減少させると、大幅な収益率の低下につながります。
築30年のアパートにおける収益率の低下は防ぎようのない事実です。
築30年のアパートは売却できる?
前述したように、築30年のアパートで今後も賃貸経営を続けるのは難しいため、早めに物件の売却を検討するのがよいでしょう。
しかし、築30年のアパートを希望する買主は少ないため、売却するにも工夫が必要です。
買取を検討
アパートなどの不動産を売却する方法としては、不動産会社に対して買主を探すよう依頼する「仲介」が一般的です。
それに対して、不動産会社に直接買い取ってもらう売却方法もあります。不動産会社は、買い取った不動産にリフォームを施して再販したり、新しく活用したりします。
一般の買主が見つかりにくい築30年のアパートでも、不動産会社であれば買い取ってくれる可能性があるでしょう。
買取の大きなメリットは、買主を探す必要がないことです。不動産会社と価格などの諸条件が合えば、約1カ月で完了するケースもあります。
ただし、不動産会社も利益を確保する必要があるため、仲介よりは価格設定が低くなる点はデメリットです。
価値のある土地だけで売却する方法も
築30年が経過しアパートの老朽化が目立った場合、思い切って建物を取り壊して、土地だけで売却する方法もあります。
土地だけを探している人もいるため、売却できる可能性が高まるかもしれません。
築年数が経過したアパートを見ると、土地の価値も低下しているように感じるかもしれません。しかし、不動産会社の担当者はフラットな目線で判断してくれます。建物の取り壊しを前提とした売却を考えることで、より確実な売却につながる可能性があるでしょう。
ノウハウが豊富な不動産会社に相談しよう
アパートの売却は、戸建てやマンションの1室を売却するよりも難易度が高くなります。まして、築30年のアパートとなると、その傾向は顕著でしょう。
そのため、実際に売却を依頼する不動産会社の選択は重要です。
担当者のコミュニケーション力や販売戦略はもちろんのこと、できるだけ地域に精通していたり、アパート売却のノウハウが豊富であったりするかを見極める必要があります。
築30年のアパートは収益率が低いですが、取得費も低くなります。投資家の中には安く購入できることに重きをおいている人もいるため、そこをうまく探し出せる不動産会社を選びましょう。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
鳥塚 正人
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





