アパートの相続税が払えない場合の対処法5つ|売却がおすすめの理由は?
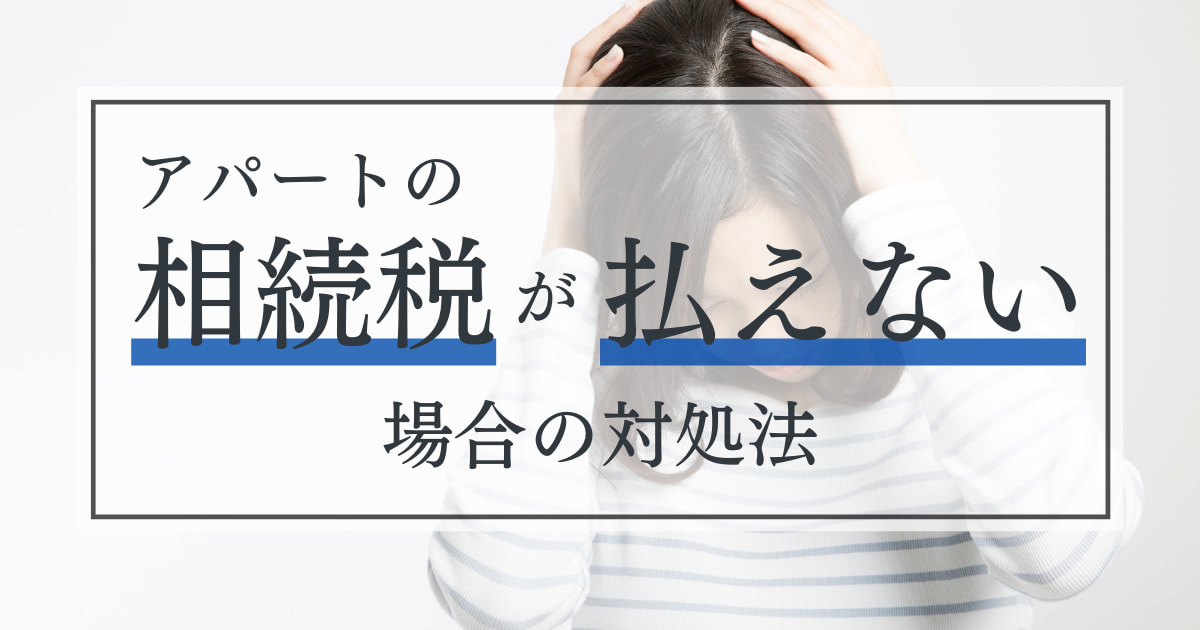
アパートなどをはじめとした資産を相続したとき、一定額以上の資産の場合は相続税が課税されます。
相続税が払えない場合は、延納や物納などの対処法を検討する必要があります。また、対処をして相続税を払うことができたとしても、今後もアパートの経営を続けていくかは、物件の現状をしっかりと把握してから検討しましょう。
この記事の目次
アパートの相続税が払えないとどうなる?
相続税を期限内に払わなかった場合、延滞税や無申告加算税がかかったり、財産を差し押さえられたりするリスクがあります。
そもそもアパートの相続税はいくらかかる?
相続税は、被相続人の関係やほかの財産額によっても変わります。そのため、アパートのみの相続税を考えることは少ないかもしれません。そのため基本的な考え方として、アパート相続時における相続税について紹介します。
相続税は財産の評価額を基に計算します。アパートの評価額は、土地と建物の評価額を合算したものです。
土地の場合、アパートが建っている土地を貸家建付地として、自用地(自分で使用している土地)の価格を基準にして計算されます。土地の評価額は、以下などによって決まります。
- 国税庁が公表する路線価(路線価がない地域は固定資産税評価額)
- 面積
- 道路にどのくらい面しているか
路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認できます。
一方建物の評価額は、固定資産税評価額に基づいて算定され、賃貸されている割合によっても変わります。
例として、以下の過程で相続税がいくらになるかについて見てみましょう。
- 被相続人:父
- ほかの相続人:母と兄弟1人
- 相続財産の合計:2億円
- 自分は法定相続(4分の1)に従い、土地・アパート合わせて3,000万円、アパート以外の相続財産を2,000万円の計5,000万円を相続する
なお、相続税は、課税金額から3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)の基礎控除分を差し引けます。
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 3人の課税金額計 | 2億円 |
| 遺産にかかる基礎控除(3人合計) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1億5,200万円 |
| 税額(3人合計) | 2,700万円 |
| 自分の相続税額 | 560万円
(※税額控除がない場合) |
相続税額は条件によって変わり複雑なため、あくまで目安としてください。
延滞税がかかる
延滞税は、定められた期限までに相続税が支払われない場合に自動的に課される、罰金のような税金です。
延滞税の利率は、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは、原則年利7.3%です。2カ月を超えると、原則年利14.6%に一気に跳ね上がるため注意が必要です。
特例があるため割合が変わる場合があります。詳しくは国税庁「延滞税の計算方法」で確認しましょ。
支払いが難しそうであれば、早めに対応策を検討する必要があります。
無申告加算税がかかる
そもそも、期限内に相続税の申告自体を行っていない場合は、延滞税に加えて無申告加算税もかかります。
もし申告自体を行っていなかった場合、税務署から申告を催促する通知が届きます。期限後1カ月以内に自主申告すれば無申告加算税はかかりません。しかし、1カ月を超えると税務調査が行われることが決定し、申告時期に応じた無申告加算税がかかります。
具体的には、以下の金額がかかります。
| 納付すべき税額に対する割合(%) | ||
|---|---|---|
| 税務調査までに期限後申告をした場合 | 5 | |
| 税務調査の通知後 | 納付額の50万円までの部分 | 10 |
| 納付額の50万円を超える部分 | 15 | |
参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
財産を差し押さえられる
相続税が支払われないままの場合、税務署は強制的に相続人の財産を差し押さえることが可能です。
財産調査が行われ、差し押さえられる財産があれば、公売によって処分され、滞納した税金に充当されます。残金があれば、相続人に返却されます。
アパートの相続税が払えない場合の対処法
相続税が払えないと損をしてしまうおそれがあるため、その前に対処が必要です。具体的な対処法を紹介します。
延納で分割払いする
相続税が期限までに一括で払えない場合、相続税の全部または一部を分割して支払う延納という方法が認められています。
ただし、延納には次の条件があり、延納利子税を支払う必要があります。
- 金銭での一括納付が困難である
- 相続税額が10万円を超えている
- 担保を提供する(※税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要)
参考:国税庁「No.4211 相続税の延納」
延納を希望する場合は、相続税の納期限までに被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に以下の書類を提出します。
- 延納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書
- 担保提供関係書類(※担保が必要な場合)
相続財産に占める不動産の割合によって変わりますが、延納できる期間は最高20年、延納利子税の税率は年率最高6.0%です。
詳しくは、国税庁の「相続税・贈与税の延納の手引」を確認しましょう。
物納で支払う
「延納しても相続税分の現金が用意できそうもない」といった場合は、相続した財産によって相続税を支払う物納という方法があります。ただし、延納と同様に利子税がかかります。
物納を行うには、以下の条件があります。
- 延納によっても金銭納付が困難である
- 物納申請財産が定められた財産の種類で申請順位によっている
- 物納申請財産が物納に充てられる財産である
参考:国税庁「No.4214 相続税の物納」
「定められた財産の種類で申請順位によっている」というのは、物納に充てられる財産には順位があり、自由に決められないということです。具体的には、以下のような順位が定められています。
| 順位 | 財産の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等 |
| 第2順位 | 非上場株式等 |
| 第3順位 | 動産 |
物納を希望する場合は、相続税の納期限までに被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に以下の書類を提出します。
- 物納申請書
- 物納手続関係書類
詳しくは、国税庁の「相続税の物納の手引 (手続編)」を確認しましょう。
金融機関から借り入れる
「相続税を払う現金がなく、物納も認められない」という場合は、金融機関からローンを借りて支払うという選択肢もあります。延納より利子が低い場合は、選択肢として検討してもよいかもしれません。
ただし、ローンの審査が通らない、ローンの審査に時間がかかると期限までに相続税の支払いができないおそれがあるといったリスクもあります。
相続放棄する
アパート以外にも相続財産がほとんどない、あるいは借金があるような場合は相続放棄をする方法もあります。
相続放棄とは、相続人であることを放棄するという意味で、資産も負債も、すべての財産を相続しないという手続きです。
申請するには、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に以下の書類を提出します。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本といった申立添付書類
詳しくは、裁判所「相続の放棄の申述」を確認しましょう。
アパートを売却する
ほかの相続財産と合わせると、アパート分も含めた相続税が高額になる可能性があります。
相続税を払うことによって、そのあとの生活に負担がかかるような状況であれば、アパートを売却して売却資金を活用しましょう。
アパート経営は、順調にいけば、家賃収入を得られて豊かな生活を可能にする事業です。しかし、その分時間と手間がかかります。
- いま元気でも、老後も事業を続けられるのか
- 自分の子ども世代が相続するときに負担にならないか
上記のような、将来的な面について考慮すると、売却することをおすすめします。
相続アパートの取り扱いに悩んだら
仮に上に挙げた対処法やほかの相続財産から相続税が払えたとして、そのアパートは相続して活用できる物件でしょうか。
特にアパート経営にいままで関わっていなかったとしたら、相続しようとしている物件についてもう少し検討する必要があるかもしれません。
物件の現状を正確に把握する
まず、空室率や入居者層はどうなっているかなど、相続予定のアパートの現状を確認しましょう。
空室率が高いとしたら、今後いままでのような収益が見込めるかどうかも検討するべきでしょう。また、もし現在の入居者が、入退去の回転が速い学生や新婚夫婦が多いようであれば、需要の高いエリアでなければ将来的に空室率が高くなるおそれもあります。
ほかにも、築年数が古ければ大規模修繕や建て替えの必要があり、収益が見合わないおそれもあります。逆に築浅の物件だとしたら、今後年数の経過とともに家賃を値下げする必要も出てくるでしょう。
また、現在の物件が収益が見込めるとしても、アパート経営は対応や判断が求められることが多いです。相続後にアパート経営を行う余力があるかについても考えてみる必要があるでしょう。
まずはアパート売却が得意な不動産会社に相談する
相続税の支払いに悩んだとき、相続放棄という選択をしがちですが、相続放棄には以下のようなデメリットもあります。
- アパート以外の相続財産も放棄する必要がある
- あとから遺産が見つかったとしても撤回できない
そのため、アパートの売却が可能かどうか一度相談してみて、難しいようであれば相続放棄について考えるとよいでしょう。
周辺相場や査定に詳しい、アパートの売却実績が豊富な大手の不動産会社であれば、判断に役立つ有益なアドバイスが得られるかもしれません。
物件を相続すべきか売却すべきか、現状と併せてどういう対処がよいのかについて一緒に考えてもらうため、まずは気軽に相談してみましょう。
この記事を書いた人
 TERAKO編集部
TERAKO編集部
小田急不動産
飯野一久
 Other Articles
その他の記事を見る
Other Articles
その他の記事を見る
一覧はコチラ
本コラムに関する注意事項
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。本コラムは、その正確性や確実性を保証するものではありません。その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。





